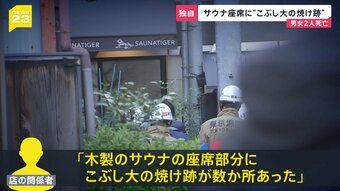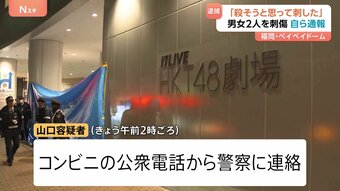「予測」精度は細かくなる一方で…
広島土砂災害から10年が経ち、現在、線状降水帯は防災の「パワーワード」のような存在となっている。それは気象庁が目指した姿で、2020年に多数の犠牲者を出した熊本・球磨川の氾濫を引き起こした線状降水帯を事前に予測できなかったことが大きい。翌年から気象庁は予算を集中的に投じて、予測に向けた取り組みを強化している。
その結果、2021年に始まった「発生情報」の発表を皮切りに、その翌年には「半日前の予測」を地方単位でスタートさせ、さらに今年からは県単位で発表するようになった。2029年を目標に半日前の予測を市町村単位で行う方針だ。

一方で、半日前の予測の「的中率」は低く、防災の観点からは問題が大きいとされる「見逃し」のケースもかなり多い。7月下旬に山形・秋田で起きた記録的な豪雨でも、線状降水帯の発生情報は発表されたが、半日前の予測情報が出ることはなかった。2029年に市町村単位での半日前予測が始まったとしても、おそらく高い確率で予想できるものにはならないだろう。
避難行動を促す“だけ”では限界も
今年6月、5段階の警戒レベルに紐付く「防災気象情報」の改善案が、気象庁などが設置した有識者による検討会でまとめられた。特別警報と警報の間に「危険警報」を導入することや、大雨や洪水、浸水などの情報をレベルの数字をそろえてシンプルにわかりやすくすることを目指すものだ。
線状降水帯の半日前予測もそうだが、情報の改善は、いかに危険な状況になる前に、住民に「避難行動を促すか」を目的に進められることが多い。このような改善はとても大事なことだ。ただ、広島土砂災害や西日本豪雨などを通じて感じるのは、事前の避難行動を促すだけで、すべての命を救うことには限界があるのではということだ。
特に土石流の場合は、木造住宅にいて直撃を受ければ命を落とすリスクが高い。垂直避難でも安全は確保できず、助かるためにはその場にいないことが重要となる。ただ、線状降水帯のように事前の予測が難しく、短時間に災害危険度が急激に高まる場合、土石流が発生するまでの猶予時間は短い。
さらに線状降水帯の発生は「夜中から早朝の時間帯に多い」という研究結果もある。つまり、土石流の場合、その場にいることで命の危険にさらされるが、予測の精度が低い状況では適切な事前の避難を促すことが難しく、情報だけで人々の命を救うには限界があるのではと感じる。