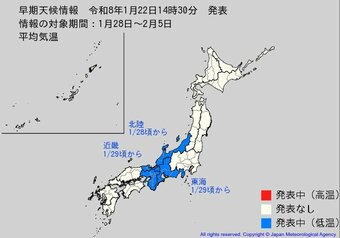かつて「総会屋」という裏社会の人々がいた。毎年、株主総会の直前になると「質問状」を送りつけて、裏側でカネを要求した。昭和からバブル期を挟んで平成にかけて、たったひとりの「総会屋」が、「第一勧業銀行」から総額「460億円」という巨額のカネを引き出し、それを元手に野村証券など4大証券の株式を大量に購入。大株主となって「野村証券」や「第一勧銀」の歴代トップらを支配していた戦後最大の総会屋事件を振り返る。
* * * * *
綺麗ごとに聞こえるが、検察とメディアは「社会正義の実現」という共通の目的をある程度共有している。しかしながら、「国民の知る権利」に早く応えるというメディアの公益性と、検察の「捜査密行の原則」は常に相反し、ギリギリのところで折り合いを探っている。
総会屋への利益供与事件は、捜査の進展とともに報道も過熱していた。野村証券の経営トップへの強制捜査をめぐり、大手新聞社が「前打ち報道」でスクープを放った。しかし、各社が当日、関係各所でカメラを構える中「前打ち報道」が予告した通りの動きはなかった。捜査の裏で何が起きていたのか、メディアと検察の関係を検証する。
前打ち報道
ある日の朝、特捜部長の熊﨑勝彦は、筆者につぶやくようにこう言った。
「総会屋への利益供与は野村証券の総務部門だけで判断できることやないで。問題は上層部がどう関わっとるのか」
「金融機関が総会屋に屈したことは悪いが、企業側だけをやるのは、不公平。理不尽な利益を要求をした総会屋も悪いやろ」
そもそも、総会屋や暴力団など「反社会組織」に対する捜査は、警視庁捜査四課などが得意とする分野だった。1982年の商法改正では、警察が主導で「総会屋排除対策」に取り組んだ。戦後最大級の「イトマン事件」絡みでは、大阪地検特捜部が元山口組の関係者や関連企業などを捜査したが、東京地検特捜部単独で総会屋や暴力団への強制捜査は、前例がなかった。1992年に摘発した「東京佐川急便事件」でも、警視庁捜査四課と合同で「稲川会本部」への家宅捜索を実施している。
また証券取引法では、証券会社が顧客に損失補てんをした場合は、顧客の要求に応えていた証券会社側だけが立件されていたが、今回は証券会社だけでなく、損失補てんを要求した側の「総会屋」小池隆一についても立件したのだ。
「顧客が損をした場合に、証券会社にクレームをつけるのは理解できるという誤った風潮もあった」 (元特捜検事)
1996年5月14日、特捜部は野村証券の元常務らを逮捕、続いて翌5月15日には総会屋・小池隆一と実弟を相次いで逮捕した。これらの供述などから、利益供与は経営トップの指示、了承があった上で実行されたものと判断し、捜査は大きな局面を迎える。
こうした中、1997年5月29日、「毎日新聞」が朝刊一面トップで「野村証券・酒巻英雄元社長を逮捕へ」「東京地検特捜部は29日にも商法違反(利益供与)の疑いで逮捕する方針を固めた模様だ」とスクープを報じた。
この「前打ち報道」は、29日に酒巻元社長を商法違反(利益供与)で逮捕することを予告するような内容であったため、検察幹部や特捜部長の熊﨑らの神経を逆撫ですることになる。