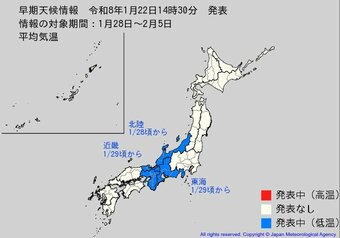検察リーク
むしろ、検察が懸念したのは、この日に酒巻元社長を逮捕した場合、「前打ち報道」を認めたことになり、次のような批判を避けたかったと見られる。
「検察が捜査を有利に進めるため、情報をメディアにリークして、国民世論を一定の方向に誘導している」
これは犯罪が明らかになることを望まない国会議員などが、メディアや検察を批判する際に、よく使う言葉「検察リーク」である。
しかし、これは筋違いの批判であり、まずはメディアが検察を情報源として報道すること自体には、何の問題もない。
それに容疑者を自殺に追い込むような容疑事実の前打ち記事や、のちの公判で立証の切り札になるような証拠を、積極的に司法記者に書かせる特捜検事はまずいない。「事件がかわいい」からである。
「検察は法廷こそが勝負の場だと思っていますから、捜査途中で立証の柱と考えている有力証拠が事前に報道されるのを極度に嫌います。被告側が公判に向けて弁解を考え、別の証拠を準備して抵抗するからです」(村山 治 元朝日新聞編集委員)
「『検察リーク』には大きな誤解があり、記者クラブに座っているだけで自動的に情報が入ってくるわけでない。P担(検察担当)の頃は「守秘義務の壁」を破るために、「夜討ち朝駆け」を繰り返し、『この記者は信用できる』という人間関係を構築するために、盆も正月もなかった。むしろこうした他社が来ない日を狙った。よく『千日回峰行』だねと言われた」 (大手新聞社 元司法記者)
もっともメディアが独自に不正や疑惑を掘り起こし、証拠も含めて特捜部に持ち込み、それがうまく事件に発展する場合もある。こうした「メディア先行型」の事件の場合は、検察としても端緒を提供してくれたメディアには「見返り」として、着手予定の見通しを情報共有するだろう。
これは検察による「情報操作」や「リーク」とは言わない。情報をくれたメディア、記者に対する「正しい情報公開」である。万が一、他社の記者が別ルートからこれらの情報を取って、先に報じてしまったら、情報をくれたメディアや記者にも顔が立たないからだ。
元朝日新聞編集委員の村山治氏は捜査機関と記者の関係について、著書でこう述べている
「国民の知りたいことを伝える記者の立場では、容疑の内容や被疑者・関係者の供述内容、捜査の状況について、検察や警察が記者に説明するのは当然のことです。国家公務員法で情報提供が禁じられている「秘密」にはあたりません。税金を使い、公権力を行使して捜査をしているのですから、それらの説明は「リーク」ではありません。
記者の立場からすれば、当局が果たすべき「説明責任」です。もちろん、当局の情報提供と報道が被疑者・被告側と被害者側の権利侵害になってはいけません。そこへの配慮を尽くしながら、当局はできるだけ情報を開示する。受け取った記者側は、情報の裏付けをとり、人権侵害や公益阻害にならないか慎重に判断した上で、記事にする。それがあるべき姿だと思います」(村山治「検察」より)