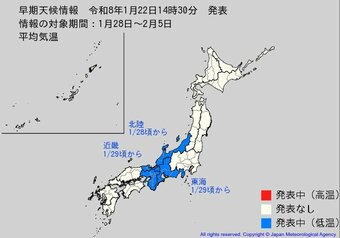強制捜査中止
これは「報道の自由」と深くかかわるテーマだが、「捜査密行主義」が原則の検察にとって、「前打ち報道」は捜査妨害につながるとして、非常にナーバスだ。「前打ち報道」を見た容疑者が「自分が捜査対象になっている」ことを察知して、口裏合わせなどの証拠隠滅工作を図ったり、逃走や自殺する恐れもあるからだ。
そうなると証拠収集が難しくなり、事件が潰れてしまう可能性がある。また情報を漏らしたのは「取り調べた検事」やその上司らではないかと被疑者側から疑われ、特捜部を信頼しなくなり、捜査協力が得られなくなる。もちろん、こうした口裏合わせなどの証拠隠滅工作自体を、詳しく立証することによって、悪質性を補強し、証拠をより強化する大きな柱になることもある。
そうした状況で司法記者は「隠密裏」の捜査情報を取るため、捜査報告が上がる検察の決済ラインや捜査対象者や参考人、弁護士などあらゆる階層への取材の蓄積から、強制捜査着手のタイミングなど展開を読むのである。
メディアはまず「第一報」が勝負どころだからであり、他社に遅れを取れば「特落ち」という烙印を押されてしまう。加えて、着手情報が取れないと、逮捕前の映像も入手できない。また容疑者がいったん逮捕されて拘置所に入ってしまうと、「犯罪行為の真相を最もよく知る」当事者の弁解を聞くことも不可能となるからだ。
どのタイミングで「前打ち報道」をするのか、着手の「Xデー」まで待つかの微妙な判断は、報道各社が最も神経をすり減らす。さらに「前打ち報道」は、それがスクープとして内容が正しかったのかどうか、すぐに結果が出るためなおさらだ。
多くの場合、報道各社は「任意捜査」から「強制捜査」に移行して初めて、「実名報道」に切り替えて続報を打っていくが、着手までの取材の蓄積が、他社との勝負を大きく左右する。
特捜部長の熊﨑は5月29日の朝、世田谷区砧の自宅で、「毎日新聞」が前打ちしたことを知り、激怒した。司法記者クラブ各社は、毎日新聞のスクープ記事を見て、関係各所に取材陣を張り付けていたが、予想に反してその日、まったく動きはなかった。
実は酒巻元社長に対する強制捜査、逮捕は中止されたのであった。「前打ち報道」は結果として、タイミングを外された形となった。
本来なら「前打ち報道」が出ると、特捜部は、捜査対象者が記事を見て自殺や逃亡、証拠隠滅を防止するため、すみやかに逮捕することもある。しかし、今回は「前打ち報道」があっても急いで逮捕する必要はなかった。特捜部はすでに元社長の自宅の家宅捜索はすでに実施し、所在や行動も把握していたからだ。