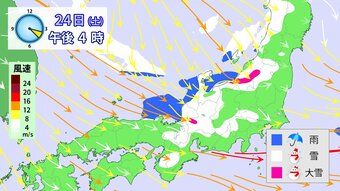大災害で必ず起こる「トイレパニック」 使えない想定できてますか?

6年前の7月、西日本の広範囲を襲った記録的な大雨・・・。西日本豪雨では交通網の寸断で食料などの物資が一時的に品薄になりましたが、上下水道のインフラ設備も大きな被害を受けたことで、長期間「トイレ」が使えなくなりました。
相次ぐ大地震や集中豪雨など大きな災害が起こると必ずといっていいほど起こるというのが「トイレパニック」です。普段、みなさんは、災害時のトイレの備えをどれくらい考えていますか?何をどう備えればいいのか、身近ながらおろそかになりがちな「災害時のトイレの備え」について、災害時のトイレ事情に詳しいNPO法人日本トイレ研究所の加藤篤代表に抑えておきたいポイントを紹介します。
災害発生後6時間以内 約70%が「トイレに行きたくなる」
石橋真アナウンサー
生活に欠かせないトイレのお話をお届けします。今この瞬間、トイレが使えなくなったら皆さんはどうしますかね。
廣瀬桃子さん
確かに考えたことがないかもしれないですよね。その生活の中に当たり前にそのトイレがあるっていう状態で今いるので…。今この瞬間に使えなくなったらって思うと、なんかぞっとしますよね。
ということで災害時のトイレの備えについて、日本トイレ研究所代表の加藤篤さんにお話を伺います。加藤さんは能登半島地震や2018年の西日本豪雨のときに被災地に行かれたそうですね。トイレに関してはどういう状況でしたか。
NPO法人日本トイレ研究所 加藤篤代表
ずっとというか、阪神淡路大震災から、災害時のトイレについてずっと取り組んできているんですが、すごく厳しい状況をお伝えすると、阪神淡路大震災から今回の能登半島地震、もちろん西日本豪雨も含めて現場では「トイレパニック」が起きています。
どういう状態かというと、トイレは大災害が起きたときでも、意外と早く行きたくなります。我々の調査によると、3時間以内に約4割の人。6時間以内までなら、約7割の人がトイレに行きたくなります。
そのときに水洗トイレは断水で水が出なくなってますし、また土砂とか地盤沈下とかで、排水設備も壊れている可能性がある。でも、それに気づかずに、多くの人が排泄をしてしまうので、便器が満杯になってしまったり、周辺が汚染されたりして、極めて不衛生な状態になりました。
不衛生→トイレを控える→水を控える で命のリスクも

石橋アナ
利用したいけど、そういう衛生面の難しさが出てくるから、その後、水を控えるようなことも出てきますよね。
加藤代表
トイレが不便とか不衛生っていうふうな状態になると、私達って水を飲むのをやめてしまうんですね。それはもう単純にトイレに行く回数を減らすためです。
でもこの水分を取るのをやめる行為をしてしまうと、エコノミークラス症候群のような、血管に血の塊ができて、それが肺に詰まったりして命を落とすことにも繋がります。
石橋アナ
能登半島地震は1月でしたけど、これも季節問わず夏であれば、洪水で断水になってトイレが使えなくなって、そこで水を控えるとなると本当に命の問題なりますもんね。
加藤代表
2018年の西日本豪雨は7月でしたよね。本当に暑かった。もう外に行って、日光を浴びることすらつらいぐらいの暑さで、仮設トイレの中も灼熱の状態だった。ですから夏場も厳しいです。
逆に能登半島地震は1月1日に起きて、ものすごく寒くて吹雪いていたりしていた。ですから寒いのもきついですし、暑いのも大変。季節に応じてどちらも厳しい状況になる。