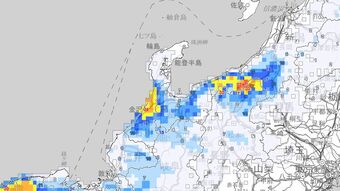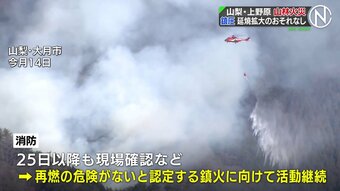あらためて、メディアの役割とは何か
川平
最後に一言だけ。とにかく沖縄で戦後ラジオを始めたのは米軍ですね。それから、テレビを始めたのも米軍。ということがあって、あそこに行くとですね、放送法とか電波法っていうのはどうなってるんだということを考えるべきじゃないかと思うんです。
これは本土でも言えることですけど、あのFEN※ っていうことはもうあって無きがごときで、だれも関心を持たないですけども、あの放送内容っていうのはですね、かなり問題のある放送内容であるんですよね。
※ 当初はFar East Network(FEN)だったが、現在はAFN(American Forces Network)となって、世界中で放送されている米軍ラジオ局(テレビ局もあり)ネットワーク。
「我が国」だとか「我が軍」だとかって言ったときには、これはアメリカ軍のことを言ってるんだっていう、そういう放送が、この主権のあるこの国でやられてる。
また、民間機が入って来るのに、ある地域では米軍の演習区域か何かになっているので、そこは飛べないようになってる。そしたら、「今度からそこは飛べるようになった」っていうのがニュースになるくらいですからね。だから、そういう意味での沖縄の米軍基地の状況というのは、やはり日本の放送メディアは、もっともっと深く見ていくべきじゃないかという気がします。
(本証言は2004年6月5日収録)
【川平朝清(かびら・ちょうせい)氏のプロフィール】
沖縄を代表する放送人。元アナウンサーであり、経営幹部として、米軍施政下の沖縄で琉球放送(RBC)、沖縄放送協会(OHK)の立ち上げに尽力した。
1927年、当時は日本が統治していた台湾・台中市で生まれる。小学校時代より放送劇に出演、台湾高等学校(旧制)在学中に陸軍に応召される。戦後は父の郷里の沖縄に引き揚げ、ガリオア資金の援助を得てミシガン州立大学に留学。この時のちの妻になるワンダリーと出会い結婚した。
帰国後、琉球放送入社、常務まで勤めたのち、本土復帰を睨んで設立された沖縄放送協会の会長に就任。本土復帰に伴ってNHK へ入局、国際協力などを担当。NHK 退局後は、昭和女子大教授、副学長、名誉教授となる。
川平家は琉球王朝で通訳・歌舞音曲を担当してきた家柄。ジョン・カビラ(川平慈温)、川平慈英の父。
【放送人の会】
一般社団法人「放送人の会」は、NHK、民放、プロダクションなどの枠を超え、番組制作に携わっている人、携わっていた人、放送メディアおよび放送文化に関心をもつ人々が、個人として参加している団体。
「放送人の証言」として先達のインタビューを映像として収録しており、デジタルアーカイブプロジェクトとしての企画を進めている。既に30人の証言をYouTubeにパイロット版としてアップしている
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版(TBSメディア総研が発行)で、テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。2024年6月、原則土曜日公開・配信のウィークリーマガジンにリニューアル。