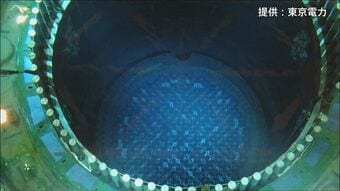分かりやすい“AかBか”を語らせるインタビューからは“卒業”する必要がある
堀潤:
(ガザ情勢が悪化した時に)イスラエルの駐日大使に聞きたかったのは「国際社会の“主語”は誰ですか?」ということ。みんな言うじゃないですか。「国際社会が、国際社会が」と。でも「国際社会」とは誰のことを言っているんだろうかと。
そしたらイスラエルのギラッド・コーヘン駐日大使は、明確に言いました。「“G7”」だと。「“G7”である日本国が、我々に対して理解を示してくれるから、日本に感謝を示したい」と言うんですよ。「国連はもう機能していない。“G7”が、我々の国際社会の“主語”だ」と。
一方、パレスチナのワリード・シアム駐日大使は、国際社会の“主語”は「国連の決定事項だ」と言うんですね。日本はようやく国連総会で、人道目的での即時停戦を求める決議に賛成してくれたから、「日本に感謝したい」と。双方の代表者が「日本に感謝したい」と言っているけれど、そこで語られる“主語”は別のものが描かれている。
今の日本の状況をすごく如実に表している。そういう声を聞いて、次に我々が何を選択するのかがようやく見えてくる。イスラエルに過度に同調するとか、逆に敵対的な反発心を抱くような言説を引き出したいとか、そういうアプローチではなくて。
本当に食べ物もなく、爆弾が目の前で落ちて、明日は我が身がというところから子供をどうするんだというお母さんたち、お父さんたちがどう救われるかを考えるために取材したいじゃないですか。
でも、短い尺に落とし込まれたニュースの世界の良くないところですけど、分かりやすい“AかBか”というのを語らせようとしてしまうインタビューがあるので、そういうのは卒業する必要があるのではないかと強く感じます。

最後のメディア空間は路上だろうなと思った
あっという間に有事が広がっていった時に、この国(日本)が、戦前と同じ過ちを繰り返さないで済むだろうかという危機を感じるんですよ。いざ大きな波が押し寄せた時に、それこそ発信しないという選択じゃなくて、「発信するな」といった空気によって、あっという間に沈黙が広がる時代が来ないとも限らない。
どこだったら発信ができるんだろうかという時に、最後のメディア空間は路上だろうなと思ったんですよ。路上が封鎖されたらもう終わりじゃないですか。だから、まだ路上が使えるうちに、「路上のメディア」を平時から作っておこうと思って「拡声器」を買ったんですよ。
香港を取材した時に、路上がメディアだったのに、横断幕さえ出せなくなって、あっという間にそういうことが起きるんだと思うと、今のうちに何かできることがあればいいと思います。