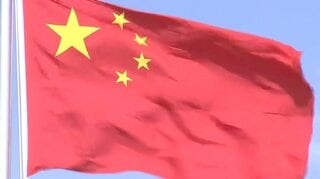まちづくりの対話を支える“入口”としての居酒屋
居酒屋で得られるものは、政策判断に直結する情報ではない。そこにあるのは、どちらかといえば「地域の空気を体に馴染ませるための助走」である。
どの言葉に笑いが起き、どの話題には反応が薄いのか。どの程度の長さの説明なら耳を傾けてもらえそうか。誰が自然に場をつなぎ、人の話を受け止めているのか。
そうした観察は、のちに住民とのコミュニケーションの場を設計するとき、具体的なヒントになりうる。
まちづくりというと、どうしても会議やワークショップの場面が思い浮かぶ。しかし、その一歩手前で「どのような文脈の中で人びとが暮らしているのか」に触れておくことは、その後の対話の成否に影響する。
居酒屋は、その文脈に近づくための入口として、無理のない距離感を提供してくれる場である。この場所でまちづくりを議論する必要はないが、そこで感じた時間の流れや言葉の手ざわりは、必ずどこかで生きてくる。
重要なのは、こうした場をあらかじめ「特別な調査の場」として構えないことである。仕事の延長として情報を取りに行くという意識を前面に出しすぎると、周囲との距離はなかなか縮まらない。
むしろ一人の客としてその場を楽しみ、自分自身も会話や時間の流れの一部として溶け込んでいくことで、自然と耳に入ってくる言葉やふるまいから、さまざまなことを知ることができるのである。
知らない土地で暖簾をくぐるという行為は、小さな決断である。行かなければそれまでだが、あえてその一歩を踏み出すことで、資料には書かれていない地域の姿が、少しだけ具体的になる。
居酒屋で過ごすひとときは、地域の将来像を左右するような大げさな場面ではない。それでも、まちづくりに関わる者にとって、その後のコミュニケーションの土台を静かに整えてくれる時間であると言ってよい。
居酒屋を、地域に入るための入口のひとつとして意識的に位置づけることは、住民との対話をより現実の暮らしに近いものにしていくうえで、思いのほか大きな意味を持つのである。
※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 社会研究部 研究員 島田 壮一郎