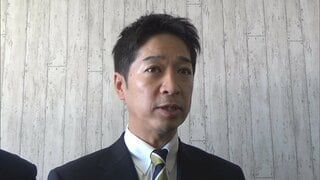「推し活」が若者と政治の距離を縮める可能性
こうしたなかで、「サナ活」のような政治における推し活は、これまでにないアプローチで若い世代に政治の接点を生み出す可能性がある。
まず、政治家を「推し」の対象として捉えることで、若い世代にとって「堅い」「難しい」などのイメージがある政治をよりカジュアルで身近なものに感じさせることができる。
特に、政治家の愛用品や日々の活動に関するSNS発信に注目することは、政治に対する心理的な距離を縮めることが期待できる。
これまで政治に関心をもちにくかった層、特に前述のとおり政治への関心が低い傾向にある若い世代の女性にとっては、「政治は自分とは関係がない」という認識を変えるきっかけになるだろう。
また、推し活を通じて政治家が推進する政策や日々の活動に関する情報へ自発的にアクセスする機会が増加するとみられる。
SNSでの「推し」の情報の共有は、友人やフォロワーなどの間で政治に関する話をする効果も見込める。
第一生命経済研究所による前述の全国調査では、「普段から、周囲の人(家族や友人、職場の同僚など)と『政治に関する話』をしている」について、「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した合計割合は、18歳~20代では32.6%で、全体の29.5%より高かった。
結果として、政治における推し活は、こうした「周囲の人と政治について話す機会」をさらに増やしたり、これまでのメディアとは異なる経路で若い世代に政治に関する話題が浸透していく可能性が期待できるということだ。
さらに、共通の「推し」を持つ人々が集まるコミュニティを形成しやすいという「推し活の特性」も見逃せない。
リアルかオンラインかを問わず、共通の興味にもとづく様々な交流は、政治についてオープンに意見交換を行う場となりうる。
このように、政治における推し活は、若者が政治に興味を持つうえでの「入り口」として機能する。
「そもそも政治に関心がない」という若い世代の女性や、「政治に対する関心は一定程度あるものの、周りの人と話す機会がない」という人にとって、日常的に政治について考えたり、家族や友人などと話すきっかけを得られるかも知れないということだ。
「推し活」を政治参加につなげるための課題と展望
その一方で、「サナ活」などの推し活が実際の政治参加へとつながるためには、いくつかの検討課題がある。
第一に、関心が一過性のブームに終わる恐れだ。
推し活は一時的には注目されるが、ブームが去れば関心も薄れてしまうことがある。
「サナ活」のように政治家個人の愛用品への興味やSNSでの流行をきっかけに、政策への理解などに進んでいくためには、さらに踏み込んだ働きかけが必要である。
消費行動やエンタメとして終わってしまっては、本当の意味での政治参加とはいえないのではないか。
第二に、政治そのものへの関心を深化させる難しさである。
個人の魅力やファッション、愛用品に対して抱く「楽しい」や「応援したい」といった印象から、複雑な社会課題の解決まで考える関心へと、どのように転換させるかは大きな課題だろう。
他の政党との政策比較や公約の実現性といった本質的な理解が深まらなければ、来るべき選挙での投票行動など、より直接的な政治参加にはつながらない。
第三に、政治における推し活が「政治的有効性感覚」を向上させるのかという点だ。
若者の投票率が低い原因の一つには「政治的有効性感覚の低さ」、つまり自分の意見や投票が政治に影響を与えないという感覚も指摘されている。
推し活を通じて政治に関心をもったとしても、自分たちの声が政治に届いているという実感を伴わなければ、具体的な政治参加にはつながらないだろう。
すなわち、推し活と政治的有効性感覚の向上との間に、どのような橋渡しをするかが重要になる。
とはいえ、若い世代が政治を身近に考える入り口として、「サナ活」などの推し活が果たす役割に期待できることも確かだ。
そこで、この推し活を「政治を自分のこと」として捉えるための主権者教育の題材にするのはどうだろうか。
主権者教育とは、「国や社会の問題を自分のこととして捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく」ための教育である。
2015年6月の選挙権年齢引き下げに伴い、主権者教育は全国の高等学校などで本格的に実施されることになった。
2022年度からは高等学校などに科目「公共」が導入され、その中に主権者教育が位置付けられた。
2023年5月に公表された文部科学省の調査によると、国公私立高等学校等のうち94.9%で主権者教育を実施している。
この主権者教育のテーマに「政治における推し活」を設定し、「なぜ共感しているのか」ということを入り口に、選挙公約や各党が議論する政策に話を広げていくこともできるだろう。
こうした教育的側面だけでなく、若い世代の政治への関心の高まりを一過性に終わらせず、継続させていくための取組みが社会全体で求められる。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主任研究員 西野 偉彦)
※なお、記事内の「図表」「脚注」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。