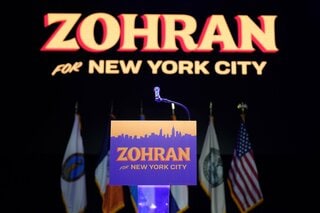(ブルームバーグ):スイスのチューリヒは、湖畔の美しい景観と中世の街並みで知られる。アルプスにも近く、何万人もの銀行員が暮らす都市だ。物価が非常に高水準で、昨年には海外駐在員にとって生活費が高い世界の都市ランキングで3位に入った。
だが、エネルギーコンサルタントのハンスヨルク・テンペルリさんは月約870スイス・フラン(約15万9000円)で、約440平方メートルの集合住宅に住んでいる。
広々としたリビングには、3つのソファとビデオプロジェクターが備えられ、2つのバルコニー、大型のキッチンやダイニングエリア、ボードゲームのコーナーまで付いている。
しかし、テンペルリさん(40)とガールフレンドが専用で使えるのは寝室とバスルーム、そして小さなリビングだけだ。残りのスペースを他の8人と共有している。「家賃は安いかもしれないが、その分、共同生活にかなりの時間と労力をかける必要がある」とテンペルリさんは話す。

世界でこうしたコハウジング形態を選択する人が増えている。テンペルリさんの住まいは「クラスターフラット」と呼ばれ、親類ではない人々と住宅を共有する。これらは学生や社会に出たばかりの若者でにぎわう寮ではなく、8人、10人、12人、あるいはそれ以上の居住者向けの物件であり、単身者や家族、高齢者などの間で人気が高まっている。
コハウジングの概念は、自由な発想が広がった1960-70年代の北欧デンマークで生まれたと指摘されることが多い。当時、共同生活への願望から共有を目的とした住宅を建設する動きが広がった。その後、他の欧州諸国にも拡大し、不動産の専門家によれば、チューリヒはこうした流れで先行する都市の一つとされている。
「20年余り前に最初のクラスターアパートを建てたときは、正気ではない、入居者は集まらないと周囲から見られていた」。チューリヒで4つのプロジェクトを持つ協同組合クラフトベルク1のマネジングディレクター、アンドレアス・エングバイラー氏はそう振り返る。「それが今では主流になりつつある」と語る。

通常、各居住者に専用バスルームとプライベートスペースを提供するクラスターフラットの多くを運営しているのが住宅協同組合だ。例えば、協同組合のメア・アルス・ボーネンは、各7-12人が住むクラスターフラットを設けており、それが11戸ある。
こうした協同組合はリビングスペースに加え、屋上庭園、電動工具やミシンを備えた作業室、音楽練習室、ホテルのような宿泊用ゲストルームなどの共用エリアを用意していることが多い。メア・アルス・ボーネンの住民は自家用車の所有を制限されているが、共有自動車の利用は認められている。
ドイツ連邦建築研究所による2018年の調査では、同国やオーストリア、スイスで数十のクラスターフラット・プロジェクトがあることが分かったが、こうした市場に関する統計を正確に把握するのは難しい。そもそもコハウジングが何を指すのか定義自体が曖昧だ。
暮らしを楽に
しかし、生活費を抑えたり、コミュニティー意識を望んだりする人が増える中、コハウジングを求める傾向は強まっていると、不動産の専門家らは指摘する。コハウジングの住民は食事や掃除を共同で行ったり、夜や週末を一緒に過ごしたり、パーティーを開いたりすることも多い。
シュツットガルトで国際建築展の責任者を務める建築家、アンドレアス・ホーファー氏は「今や住宅開発提案の多くにクラスターフラットの要素が求められている」と明かす。
メア・アルス・ボーネンの創設メンバーで、マネジングディレクターを務めたこともあるホーファー氏は「10年前はそうではなかった」と振り返り、「孤独は現代社会が抱える大きな問題の一つであり、クラスターフラットが日々の暮らしを少し楽にしてくれる」と話す。

コハウジングに特に適しているとされるのが高齢者層だ。55歳を超えるチューリヒ住民を対象にした22年の調査では、80%が多世代世帯で暮らしたいと考えており、半数がコハウジングに関心を寄せていた。コハウジングは高齢者施設に入ることなく、仲間や支え合えるコミュニティーが得られる選択肢を提供する。
チューリヒの高齢者の住まい探しを支援する団体でプロジェクトを担当するニナ・シュナイダー氏は、「高齢者は広過ぎるアパートや、顔見知りのいない地域で一人暮らしをしている場合が多い」と説明。「共用エリアで他の人々と交流することは、特に貴重な経験だ」と語る。
チューリヒがこうした共有型モデルを積極的に採用できる背景には、協同組合、または市が住宅ストックの20%超を保有しているという事情がある。同市がコハウジング開発の資金繰りや規制の枠組みを設けており、協同組合や民間開発業者に土地を分譲する際には、詳細な建設提案の提出を求めるのが一般的だ。
プロジェクト候補は持続可能性やイノベーション、そして中間層が価格高騰で排除されるのを防ぐため、相場以下の家賃を提供できるかどうかといった観点から評価される。チューリヒ市内の賃貸物件の空室率はわずか0.07%となっており、スイス政府が不足と見なす1%の水準を大きく下回っている。だが、協同組合や市営の5万5000戸の住宅は、民営と比べて約25%安い。

コハウジングは欧州だけでなく、オーストラリアやニュージーランド、米国などにも広がりつつある。ニューイングランドや太平洋岸北西部などでプロジェクトが立ち上がっているが、米国での拡大ペースは鈍い。米国人は住宅を主要な運用資産と見なす傾向にあるためだ。
これに対し、コハウジングの仕組みでは、住民は物件を賃貸するか、協同組合の持ち分を購入し、退去時にはほぼ利益を得ることなくそれを売却するのが一般的だ。
もう一つの課題は、米国では住宅支援が主に低所得者を対象としているのに対し、欧州諸国ではより幅広いアプローチが採用されている点だ。ハーバード大学住宅研究共同センターのリサーチフェロー、スザンヌ・シンドラー氏は「チューリヒには協同組合住宅に住んでいる富裕層さえいる」と話す。
共同生活
チューリヒ市で住宅政策を担当するフィリップ・コッホ氏は、同市のようにコハウジングが盛んな都市でも、住宅市場全体に占めるコハウジングの割合は今後も比較的小さなものにとどまると指摘する。
関心は高まっているものの、共同生活に適応するのは容易ではなく、従来型のアパートに比べて住民の入れ替わりも多くなるといい、「応募者の多くは実際にどんな生活が待っているか十分理解できていない」とコッホ氏は語る。
コハウジングの利点の一つは、人口密度の高い都市において1人当たりの居住面積を減らせることだが、「この違いだけで住宅不足が解消されるわけではない」とコッホ氏は言う。実際には、より多くの面積を必要とすることさえある。
例えば、チューリヒ西部で進められているクラフトベルク1の新プロジェクトでは、クラスターフラットの1人当たり面積は平均約34平方メートルで、同じ開発内の一般的なアパートの32.5平方メートルよりわずかに広い。ただ、いずれも市全体の平均を下回っている。

同プロジェクトはコッホ地区にあり、最大10の寝室を備えた非クラスター型のコハウジング住戸や、「ローバウ(大まかな建物)」と呼ばれる8戸の住居も含まれている。これらは4メートルの高さの天井を備えたコンクリートシェルとして引き渡される予定で、バスルームとキッチンのみが設けられ、あとは居住者がレイアウトを担うことができる。
この建物を設計したチューリヒの建築事務所スタジオ・トラクスラー・ホフマンの建築家、ノエミ・エンゲル氏は「空間的なゆとりがあり、多くの可能性が広がる」と話す。
柔軟な未来
チューリヒの建築士、モリッツ・ケーラーさんはこの開発プロジェクトにある6戸のクラスターフラットの一つに注目している。それぞれ最大12人が暮らす想定で設計されている。
ケーラーさん(29)は現在、市中心部で2つの寝室がある集合住宅に割安な条件で住んでいるが、クラスターフラットからもたらされる強いコミュニティー意識に魅力を感じているという。ケーラーさんと現在のルームメートは、来年入居開始予定のコッホ地区の住戸の一つに申し込むため、仲間を集めている。
ケーラーさんは同僚の多くが結婚して家庭を築くのを目にする一方で、もっと柔軟なライフスタイルを望んでいる。従来のスタイルは「あまり現代的とは思えない」といい、クラスターフラットであれば、「柔軟な未来に対応でき、いつかボーイフレンドと一緒に住みたいと思うかもしれないし、子どもを持ちたいと思うかもしれない。そんなときにも、引っ越しを何度も繰り返さずに済む」と語った。
(原文は「ブルームバーグ・ビジネスウィーク」誌に掲載)
原題:Living With a Dozen Strangers to Ease a Housing Crunch(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.