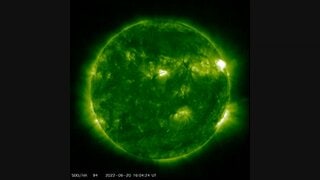(ブルームバーグ):米国による関税措置で企業がコストカット志向に回帰する恐れがあるー。内閣府は2025年度の年次経済財政報告(経済財政白書)でこう警鐘を鳴らした。デフレ経済への後戻りを回避するためにも、2%の安定的な物価上昇率の実現とともに、賃金と物価の好循環を回し続けることの重要性を唱えている。
29日公表の白書では米関税の影響について、輸出数量や生産指数、雇用などの指標に特段の影響を与えていないものの、追加関税の発効直後には北米向け乗用車輸出価格が大幅に低下していると指摘。こうした動きが広がれば「雇用・賃金、設備投資、個人消費なども下押しされるリスクがある」とし、企業が「コストカット志向に回帰する可能性に留意が必要」だと記した。
このようなリスクへの備えとして物価安定の重要性を強調。企業や家計の予想物価上昇率が2%で定着すれば「消費や投資の最大化を図ることが可能となる」と指摘した。また、「現実の物価上昇率が2%程度となるよう着実な金融政策運営が継続すれば、結果として安定的なマクロ経済環境の形成につながる」としている。
米関税発動前の1-3月に日本経済は縮小した。米国は4月から全輸入品に一律10%、自動車・自動車部品に25%の関税を適用。上乗せ関税の一時停止期限の8月1日を前に日本の税率は自動車・同部品を含め15%で合意したが、企業の価格設定や設備投資は消極化しかねない。テクニカル・リセッション(2期連続マイナス成長)も懸念される中、賃金・物価の好循環が景気の下支えの重要な鍵と位置づけた。
白書では自由貿易体制の重要性にも言及。自由貿易協定の締結は、貿易創出効果により、相手国との間の輸出入を増加させている。「同志国や地域と連携して、世界貿易機関(WTO)体制を中心とするルールに基づく自由で公正な国際経済秩序の重要性を示していくことが重要」だと主張した。
分岐点
経済財政白書は内閣府が年1回まとめる報告書で、日本経済の実態に関して幅広く分析する。今年度の白書の副題は「内外のリスクを乗り越え、賃上げを起点とした成長型経済の実現へ」とした。現状認識では、物価上昇の継続による個人消費の低迷とトランプ米政権による関税措置という「経済への逆風」を乗り越え、「賃上げを起点とする成長型経済」に移行できるかの分岐点にあると記した。
日本経済は「経済学的に言えばインフレの状態にある」との認識を示す一方、再びデフレに後戻りする見込みがないとまでは言えないと指摘。デフレ脱却に関しては、企業の賃金設定行動や価格転嫁の進捗、物価上昇の品目別の広がり、家計や企業の予想物価上昇率など「ミクロ的観点を含め、さまざまな指標やデータを総合的に考慮」し、慎重に判断する方針を改めて示した。
政府は01年3月の月例経済報告に緩やかなデフレにあるとの見方を示した。13年12月にデフレの文言が削除され、デフレ状況にないとの認識が示されたものの、脱却したとの評価には至っていない。
全国消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は6月まで日本銀行が物価安定の目標とする2%を39カ月連続で上回り、堅調な推移が確認されている。関係者によると、日銀は30、31日の金融政策決定会合で、コメを中心とした食料品価格の上昇を反映し、25年度のコアCPI見通しの上方修正を検討する見込みだ。今後の金融政策運営は、米関税による影響の見極めが重要となる。
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.