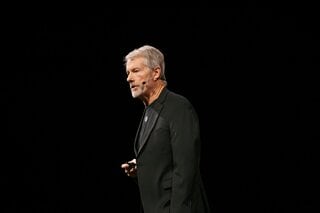OpenAIの内幕:非営利の組織から「帝国」への変貌
ハオ氏がOpenAIに注目した理由は、彼らが「公共の利益のためにAIを開発する非営利の研究機関」という理想を掲げていたからでした。
実際、OpenAIは非営利組織として設立されています。
営利目的に縛られない新たなイノベーションモデルになり得るかもしれない。そんな期待を胸に、彼女は先入観なく取材に臨みます。
2019年8月には、3日間の滞在取材も許可されました。しかし、取材を通して見えてきたのは、理想とはかけ離れた実態でした。

「3日間の滞在取材と従業員へのインタビューで分かったのは、OpenAIも本質的にはほかのシリコンバレー企業と何ら変わらないということでした」
その兆候は、OpenAIが方針を転換し始めた時に現れます。
当初はすべての研究成果をオープンソース化すると公言していましたが、2019年初頭、ChatGPTの前々世代にあたる「GPT-2」を「悪用の危険性」を理由に非公開としたのです。
科学界から批判が上がり、最終的にモデルは公開されましたが、これは彼らが透明性を失いつつある重要なシグナルだったとハオ氏は指摘します。
「社内の人に話を聞くと、『これほど秘密主義な組織はなかなかない』という声が相次ぎました。公の場で語られるストーリーと、社内の現実との間には大きな『食い違い』があったのです」
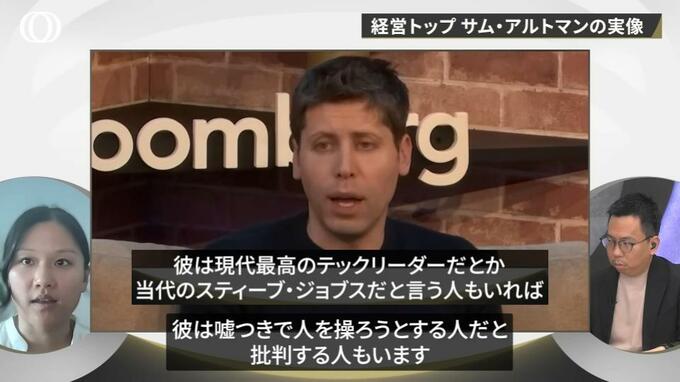
この「食い違い」に焦点を当てたハオ氏の記事に、OpenAI側は強い不満を抱き、彼女を“出禁”にします。
「AIの帝国」と植民地主義、4つの共通点
ハオ氏は著書で、OpenAIのような企業を「AIの帝国」と呼び、かつて植民地主義を展開した帝国との4つの共通点を挙げ、以下のように主張します。
①資源の支配
帝国が他国の土地や資源の支配権を主張するように、AI企業はインターネット上の膨大なデータを「公有財産だ」と主張し、アーティストや作家の知的財産を正当化して利用します。
②労働の搾取
AI開発の裏では、安価な労働力が搾取されています。
ハオ氏は、OpenAIがケニアの労働者を時給わずか数ドルで雇い、AIに有害なコンテンツをフィルタリングさせるための過酷な作業に従事させていた実態を取材しました。
心的外傷を負い、家族との関係まで壊れてしまった労働者もいたといいます。これは「一部の人間性を踏みにじることを正当化する帝国の論理そのものだ」と彼女は断じます。
③知識の独占
破格の報酬で大学からトップ研究者を引き抜き、AIに関する知識の生産を民間企業が独占しています。
これにより、企業にとって都合の悪い研究結果は検閲され、技術のリスクや限界が正確に社会に伝わりにくくなります。
④「善と悪」の構図
「悪の帝国(Googleや中国)が危険なAIを開発する前に、善の帝国である我々が世界を救うAIを完成させなければならない」。
このような善悪二元論の物語を使い、自らの権力集中と資源の独占を正当化します。これは、かつて植民地支配を正当化するために使われたレトリックと酷似しています。