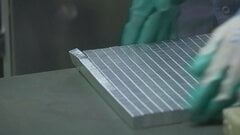物価上昇を目指してきたのに物価高対策
そもそも政府も日銀も物価上昇率2%を目標に掲げ、デフレ脱却を目指してきました。いわば物価高を目指してきたのに、今、物価高対策が選挙の争点になっているというのも、不思議な話です。
確かに、足元の物価上昇率は3%台後半と、想定より上振れしています。しかし、エネルギーと食料品、とりわけコメといった特定分野の価格上昇の影響が大きく、これが消費生活に直接の打撃をもたらしています。その意味で、エネルギーやコメなどの価格上昇を緩やかにする取り組みは重要ですが、政策の方向性は、物価を抑えるのではなく、あくまでも物価高に苦しむ生活支援という位置づけを明確にすることが大事だと思うのです。
2%の物価上昇というモメンタムを維持しながら、賃上げと成長を続けることが目指すべき姿です。
鍵は賃金上昇、そのために投資を
賃金が物価に追いついていないのであれば、賃金を上げ続けることが王道です。5%台の賃上げをさらに来年以降も続けられるようにするには、やはり経済主体の生産性の向上が欠かせません。生産性向上のためには、設備投資の拡大や人手不足への対応が必要です。今は、供給制約を克服するための政策が、むしろ効果を発揮する局面です。
全員へのバラマキではなく、設備投資の促進や労働力の流動化などに財政資金を振り向けるほうが、成長に効果的なのではないでしょうか。選挙戦では、生産性の向上や経済成長を、どのように実現するかという具体論をもっと聞きたい気がします。