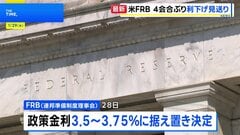管理職志向の低下や長期就業を望まない声の広がりは、男女を問わず、世代を越えて進行している。
本レポートでは、ニッセイ基礎研究所が毎年実施している「被用者の働き方と健康に関する調査」の結果をもとに、性別および年齢別のキャリア志向の違いや、ここ5年間の変化を分析した。
調査からは、特に若年層で長期的な働き方や管理職を選択肢としない傾向が強まっていることがうかがえた。また、管理職よりも専門性の高い働き方を志向する動きもみられた。
企業側が多様な人材の登用を模索するなかで、こうした志向の変化が今後の人材戦略にどう影響するのかも注目される。
企業における女性管理職や女性役員の登用に関して数値目標が掲げられている。
例えば、内閣府の「第5次男女共同参画基本計画(2020年策定)」では、指導的地位に占める女性の割合を30%程度とすること、「女性版骨太の方針」では、プライム市場の上場企業の女性役員比率を30%とすること等が目標として掲げられている。
その背景には、女性のキャリア形成や待遇改善といった労働者個人の働き方の選択肢を広げる動きに加え、女性活躍に対する評価やダイバーシティの推進を通じて経営の多様性を高めたいという企業側の狙いがある。
なかでも女性の登用は、多様な人材活用を象徴する取り組みとして注目されてきた。
近年、役員への女性登用は増加しているが、その約9割は社外からの登用であるとされている。
管理職や役員に関して、社内登用を進めるにあたっては、経験を積んだ人材の不足等や、昇進にともなう重責を好まない傾向があることが、課題としてあげられることが多い。
さらに、人々のキャリアビジョンは、性別や年代だけでなく、時代の価値観によっても変化しており、最近では、男性を含めて管理職になりたがらないということも指摘されている。
会社員は、長期的な働き方としてどのようなコースが望ましいと考えているのだろうか。
本稿では、ニッセイ基礎研究所が被用者を対象に毎年実施している「被用者の働き方と健康に関する調査」から、「あなたにとって、長期的な働き方として次のうちどのようなコースが望ましいと考えますか」という問いの回答結果をもとに、人々が今どのような働き方を望んでいるのかを探りたい。