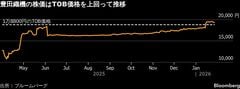発動可能性はどれほどあるのか
第899条項の発動は、国が差別的とみなした国に甚大な影響を与える一方、米国自身も金利上昇や相手国からの報復、エスカレーションによる米国離れの加速といったリスクを抱える諸刃の刃である。
そうした意味では、軽々しく発動できるものではない。したがって、第899条は、いざというとき行使できることを見せて、相手に譲歩を迫る脅しとしての役割が大きいようにと思われる。
ただ、第899条項の構成は、初年度に5%の追加課税を行い、数年かけて課税を強化していく仕組みであり、段階的な強化で時間制限を設けている点は、発動した際の交渉を有利に進めようとの意図が感じられる部分として、米国側のリスク・コントロールがあるようにも感じられる。
トランプ大統領は、関税政策を発動してもすぐに撤回するなど、朝礼暮改の政策運営を繰り返し、世界的にTACO「Trump Always Chickens Out(トランプはいつもビビってやめる)」との造語が広がっている。
ただ、6月21日には、初めてイラン本土への攻撃に踏み切ったように、思わぬところでアクセルを踏み抜く可能性は否定しきれない。
加えて、トランプ大統領は第899条項以外にも、1月20日の就任時の大統領令で、内国歳入法891条に基づく調査を進めている。
この条項も、不公正な外国税の導入国の法人や企業の所得に追加課税するものであり、大統領が宣言すれば税率は2倍になる。
日本は関税交渉に加えて、税制面でも交渉対象となる可能性が高く、第899条項の扱いがどうなるか注視しておく必要がある。
仮に、第899条項が今の形で残るとすれば、日本が取りうる選択肢は、個人や企業への影響を緩和する何らかの手段を見つける(あるいは無視する)か、軽課税所得ルールの2026年4月以降の適用を見直す、または、米国との交渉で何かを差し出して課税対象から外してもらうしかない。
いずれにしても、これから数日、数週間の議論には、注目しておく必要があるだろう。
(※なお、記事内の注記については掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください)
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 総合政策研究部 准主任研究員
鈴木智也)