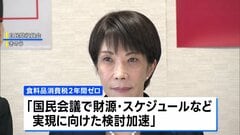<注目点>
6月22日の東京都議会選挙に続き、7月には参院選選挙(20日との声が多い)も予定されている。金融政策については、トランプ関税の霧が晴れない中、7月の利上げを見込む向きはそもそも少数派であるが、政治日程を踏まえると、利上げはなお更考えにくいとの見方は多い。
ここで参院選の概要を整理する。今回の参院選は、248議席のうち半数にあたる124議席が改選される他、東京選挙区の補欠選挙(1議席)が同時に実施される。現在の議席数は、自公で合計140を占める(野党は99議席、欠員9、出所は参議院HP)。改選対象は自民党が52、公明党が14で合計66、非改選は自民党が61、公明党が13で合計74となっている。したがって、今回の選挙で自公が51議席を確保すれば、125議席となり過半数に達する。ここが重要な「勝敗ライン」となる。仮に過半数割れとなれば「石破おろし」の連想が広がり、またその先には高市総裁の誕生が意識されるだろう。その場合、金融市場では金利のツイスト・スティープ化、円安・株高が想定される。言わずもがな高市氏は、日銀の金融引き締めに批判的であり、積極財政論者として認識されている。消費税減税と防衛費拡大の予想が相俟って、国債増発観測が生じ、(超)長期金利には上昇圧力がかかろう。
さて話を金融政策と選挙の関係に戻すと、日本に限らず「選挙期間中の金融引き締めは、中央銀行が『自重』する」という暗黙の掟がある。金融政策決定会合は7月31日に実施されるため、参院選後となるが、市場との対話(≒事前に情報を与える)を重視する現日銀の行動様式を踏まえれば、利上げをする場合、7月中旬頃には金融市場に何らかの「合図」を送る必要があり、選挙期間にかぶってしまう可能性がある。そうした問題を避けるために9月や10月以降に先延ばしにするという選択肢は、ある意味で自然にみえる。
選挙期間中に日銀が動かない・動けないのは円高と株安を誘発してしまう恐れがあり、それが与党に対して不利に働き、政治的な中立性を保てないから、という考え方がある。もっとも、現在は円高が歓迎される環境にあるという点において、過去と事情が異なる。お米の価格が高止まりし、生活コストが圧迫される中、輸入物価の低下に資する円高は政治的な波紋を呼びにくい。この点において日銀は、選挙を気にせず自由に動ける面がある。
また先週来のイラン・イスラエルを巡る紛争とそれに伴う原油価格上昇が、日本のインフレ率を更に押し上げる可能性も浮上してきた。日本時間6月23日午前9時時点でWTI原油は76ドル程度と、前週末対比での急騰は回避されているとはいえ、60ドル割れで推移していた5月上旬と景色は大きく変わっている。日銀は5月1日に発表した展望レポートで、原油価格の前提を下げたことなどから、物価見通しを下方修正したが、原油価格がこのままの水準を維持するならば、7月の展望レポートでは物価見通しを上方修正する公算が大きい。原油価格の上昇が、日銀が言うところの「基調的な物価上昇率」を押し上げる可能性は限定的と考えられ、むしろ交易条件の悪化を通じて、やや物価下押し要因にさえなり得そうだが、それでも利上げを見送り円安が加速すれば、表面的な物価上昇率には上昇圧力が生じる。
これらを踏まえると、日銀の7月利上げは選択肢から排除すべきではないように思える。目下の金融政策運営にあたって最重要要素である、日米の通商交渉に大幅な進展がみられれば、日銀は急速に利上げ方向に舵を切るのではないか。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 藤代宏一)