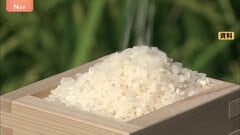職場の同僚が「銀行で両替してきた」と言って見せてくれたのが、ミャクミャクが刻まれた500円の記念貨幣だった。大阪・関西万博を記念して財務省が発行した法定通貨であり、買い物にも使える。中央は銀白色、外周は黄金色の二層構造で、金属の質感を活かした彫刻によりキャラクターが立体的に浮かび上がる。実際には通常の500円硬貨と同じ素材・サイズ・重量であり、見た目の特異性とは裏腹に、日常の中に溶け込みやすい設計となっている。
記念貨幣という存在自体は目新しいものではない。今回の万博に際しても、10,000円金貨や1,000円銀貨といった高額かつ豪奢な貨幣がすでに発行されている。しかし、それらは専用申込による購入制であり、日常生活ではほとんど目にする機会がない。一方で、この500円記念貨幣は、全国の金融機関を通じて実際に流通している。日常の延長線上にある、“公共空間で多くの人に触れられる記念”として、多くの人の目に触れる存在となっている。
こうした中、先日覗いた東京の複数の書店では『大阪・関西万博ぴあ』が品切れとなっており、Amazonでも一時「お届けまで1週間以上」との表示が出ていた。関西主導のイベントではあるが、東京でも徐々に機運が高まってきたことの一端かもしれない。
そのような中、この500円貨幣を手に取ったとき、改めて感じるのは——これは単なる記念グッズではなく、国家的事業の象徴であり、公共性のある資金の使途や優先順位のあり方を問いかける存在でもある、ということである。
国家が「記念する」とはどういうことか
日本における記念貨幣の歴史は、1964年の東京オリンピックにさかのぼる。100円銀貨が最初の発行例である。以降、天皇陛下の御在位や沖縄の本土復帰、長野冬季五輪、東日本大震災の復興支援など、国として「記憶に残すべき節目」にあたって記念貨幣が発行されてきた。
これらは単なる収集品ではない。記念貨幣の発行は、法律に基づいて内閣が閣議決定を経て行われるものであり、発行の対象となる出来事は、形式的には「国家として記念に値するもの」として一定の重みをもって扱われている。今回の500円記念貨幣も、発行枚数が約220万枚とされ、全国の金融機関で両替を通じて流通している。近年では2020年東京オリンピック・パラリンピックでも500円を含む複数の額面の記念貨幣が発行されたが、そのうち500円貨と100円貨は今回と同様に、銀行窓口での引換えを通じて流通する形式が採用された。
ミャクミャクの硬貨も、かわいらしさの裏に、そうした行政手続きの重みや国としての思いを背負って存在している。