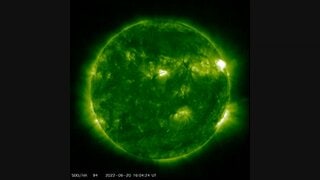(ブルームバーグ):公正取引委員会は15日、米アルファベット傘下のグーグルに対し排除措置命令を行ったと発表した。同社がスマートフォンメーカーに対し、自社アプリやサービスを優先的に扱うように求めていたことが独占禁止法に違反すると判断した。
発表によると、グーグルはスマホメーカーに対し、グーグルプレイの使用を許可する条件として、「グーグルクローム」を搭載し、初期画面に配置することなどを求めていた。また、検索広告の収益の支払いの条件に、競合他社の検索サービスの排除を要求していた。
公取委によると、グーグルがクロームなどを有利な場所に配置するよう求めていたのは、昨年12月時点で少なくとも6社に上った。
公取委はグーグルに対して違反行為の取りやめのほか、こうした行為が行われていないか第三者による監視と報告を5年間求めるとした。今回の措置に従わない場合には、グーグルは過料や刑事罰の対象になる可能性があるという。
監視強化の流れ
公取委の発表は、米国との関税交渉を担う赤沢亮正経済再生担当相の訪米を控えたタイミングとなった。折しも米国通商代表部(USTR)は、日本の「デジタルプラットフォーム取引透明化法」が、米企業の競争力を損なうと批判している。
米国は日本に対して財の分野では赤字になっているが、サービス分野は黒字だ。サービス分野には、グーグルのアンドロイド関連のライセンス料や広告収益も含まれる。
今回の公取委の命令は、米テック企業に対して初の措置となるが、実情としては各国の規制当局が市場支配への監視を強めている流れがある。昨年8月には、グーグルが自社の検索エンジンをスマホやウェブブラウザの優先検索エンジンに初期設定してもらうため、アップルやサムスン電子に支払いしていることが、反トラスト法(独占禁止法)に違反すると米連邦地裁が判断を下した。
グーグルが排除措置命令の対象になったことに関連して公取委は、同様のケースは欧州や米国でも起きており、特定の米企業を狙い撃ちしたということではなく、各国と同じように粛々と対応していると説明した。
これに対してグーグルは、調査結果に遺憾の意を表明した上で、今回の命令を精査し今後の対応を慎重に検討するとブルームバーグの問い合わせにコメントした。公取委は2023年10月に審査を開始し、昨年12月には日本経済新聞などが独占禁止法違反と認定する見通しだと報じていた。
(グーグルのコメントを追加しました)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.