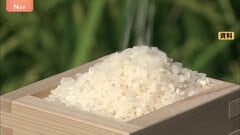日常生活の中では、知らず知らずのうちに、予想や予測をしていることがある。
例えば、
毎朝、天気予報を見て傘を持っていくかどうかを決める。
電車通勤の場合は、混雑具合を予測して出発時間を調整する。
自動車通勤の場合は、渋滞しそうな道を避けてルートを選ぶ。
仕事を行うときには、締め切りを見越してスケジュールを組む。
仕事からの帰りには、家の冷蔵庫の中身を思い出して、不足しそうな食材をスーパーマーケットで買う…。
といった感じだ。
こうした予想や予測は、何らかの根拠に基づいて行われることが一般的だ。
天気予報や渋滞予測のように、メディアで報じられる情報があるときには、それが大いに参考になる。
そういう情報がない場合はどうするか。たいていの場合、これまでに経験したことをもとに何らかのパターンや法則を見つけて、それを予想や予測にいかすことになるだろう。
そうしたパターンや法則は、どこまで信頼できるものなのだろうか。今回は、この点について、数学で出てくる数列を題材として考えてみたい。
高校数学で出てくる等比数列とは…
数列と言えば、高校生が数学で学ぶ重要な内容だ。その内容は、社会のさまざまな分野に応用されている。
数列の中では、等差数列や等比数列が基本的だ。等差数列は、各項が一定の差で増加していったり、減少していったりする数列をいう。等比数列は、各項が一定の比で増加していったり、減少していったりする数列を指す。「一定の差」や「一定の比」は、それぞれ公差、公比と呼ばれる。
高校数学では、nを1以上の整数としたうえで、第n項をnを使った式で表したり、初項から第n項までの合計をnを使った式で表したりすることが、テストで出題されることが多い。
この数列のうち、等比数列を用いて、次のような問題が考えられる。
(等比数列)
初項1、公比2の等比数列を考えます。
初項、第2項、第3項、第4項、第5項の順に並べると、1, 2, 4, 8, 16となります。
それでは、この数列 (1, 2, 4, 8, 16, 〇, …) の第6項 〇 に入る数は何でしょうか?
公比2の等比数列だから、前の項の2倍となるよう数が増えていく。第6項は第5項16の2倍で32だ。第n項をnを使った式で表すとすると、2^n-1 (2のn-1乗)となる。
nの階乗の約数の個数の数列は?
唐突に「nの階乗の約数の個数」などと言われても、なかなかピンとこないだろう。
こういうときは、試しにいくつかやってみると理解が進みやすい。
n=1のとき、1!=1で、1の約数は1だけなので、約数の個数は1個。
n=2のとき、2!=2で、2の約数は1と2なので、約数の個数は2個。
n=3のとき、3!=6で、6の約数は1, 2, 3, 6なので、約数の個数は4個。
n=4のとき、4!=24で、24の約数は1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24なので、約数の個数は8個。
n=5のとき、5!=120で、120の約数は1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120なので、約数の個数は16個。
確かに、問題文に示されている通り、1, 2, 4, 8, 16という数列になっている。
それでは、〇に入る数は何だろうか。
ここで「この数列は、初項1、公比2の等比数列と同じなのではないか」という気がしてくる。
「初項から第5項まで同じなのだし、2つの問題を上下に並べて問題文を少し違う表現にしているが、『実は同じものでした』というオチなのではないか。数学的帰納法か何かを使えば、この数列の第n項が2^n-1であることが証明できるのだろう。ということで、〇に入る数は、32に違いない…。」
こんなふうに考えてしまうと、これまでのパターンや法則にとらわれてしまったことになる。
地道に6!つまり720の約数を記していくと、1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 48, 60, 72, 80, 90, 120, 144, 180, 240, 360, 720となり、約数の個数は30個。〇に入る数は、30となる。
このnの階乗の約数の個数の数列は、1, 2, 4, 8, 16, 30, 60, 96, 160, 270, 540, 792, 1584, 2592, 4032, 5376, …と続いていく。
初項1、公比2の等比数列とは異なる形で、増加していく。
(なお「ルジャンドルの公式」を使うと、第n項を数式で書き表すことができるが本稿では割愛する。気になる方は“Legendre's formula”のキーワードでネット検索をしていただきたい。)