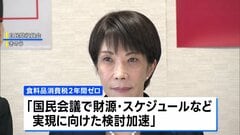円安による物価高の場合、株価(資産価格)の上昇が消費マインドを支えていた
物価高によって家計の消費マインドが悪化するという流れは、今に始まったことではない。コロナ後はエネルギー価格の上昇や円安による高インフレが常態化しており、下方リスクは大きくないという考え方もできるだろう。しかし、生鮮食品の価格上昇によって消費マインドはさらに悪化する可能性が高いと、筆者はみている。
このように考えるのは、そもそも23年以降は消費者態度指数(前年同月差)と実質賃金の連動性が低下していることに注目しているからである。22年までは実質賃金の低迷に合わせて消費者態度指数は低下したが、23年はさらに実質賃金が低下したのにもかかわらず、意外なことに消費者態度指数は回復した。この背景として説明できそうなのが、株価など資産価格の上昇である。この間も、消費者態度指数の動きとTOPIXの前年比の動きはかなり連動していた。この点に注目すると、前述した23年の消費者態度指数と実質賃金の動きの乖離については、実質賃金は悪化していても資産価格が上昇していたことから消費マインドは悪化しなかった(むしろ改善した)と考えることが出来る。22年に流行した「悪い円安」の議論以降、円安は物価高を介して家計にはネガティブだという認識が広がっているが、実際には資産価格の上昇(資産効果)もしっかりと反映されていたようである。
以上を整理すると、円安によって実質賃金が低迷したとしても円安によって株価が上昇すれば家計のマインド悪化は限定的になる可能性がある。しかし、現在の生鮮食品の価格上昇が主導したインフレが株価を押し上げる可能性はほとんどないと考えられ、家計にとっては実質賃金の目減りというマイナス面だけが意識されるだろう。家計の消費マインドへの影響を考える場合、インフレの内容にまで注目する必要がある。

(※情報提供、記事執筆:大和証券 チーフエコノミスト 末廣徹)