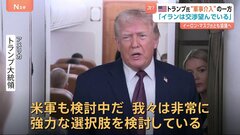社会の「当たり前」「常識」の変化に合わせた文脈の生成
一昔前は、シェアも食べ残しの持ち帰りも、「貧乏くさい」アクションとされた。現在もそうした感覚をもつ人は少なくない。しかし、「シェアは合理的だし、つながりなどの付加価値もあって新しい」「食べ残し持ち帰りは合理的だし、食品ロスゼロに向けた意識高い系アクション」といった感覚は、着実に定着している。「当たり前」「常識」は時代とともに変化するのである。
こうした時代や状況の変化に合わせて、消費者に刺さる文脈でのエシカル消費推進や規制改革を行うことが、長期的な視点での定着につながる。エシカル消費は、既述したフランスの事例のように、インフレで消費者が行動を変えることで簡単に廃れてしまうようなアクション・トレンドとしてではなく、日常的なマインドとして根付かせる工夫が求められる。むろん、宗教的な禁忌が多様に存在するように、エシカル消費においても、ヴィーガンやアニマル・ウェルフェアなど「エシカル」のあり方や考え方も人それぞれである。そうした中、いかに異なる価値観を受容しつつ自分の消費行動における意義を見出し、ウェルビーイングな日常を自ら形成するかが重要となる。
なお、「エシカル消費」という言葉は出現して相当の年月が経つが、一般の消費者における認知度は高くない。しかし、ゴールは言葉の定着ではなく、意識とアクションの定着である。この点に鑑みて、手段と目的をはき違えないよう留意したうえでエシカル消費を推進することが、これからの社会に求められる。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 常務取締役・ライフデザイン研究部長・首席研究員 宮木 由貴子)