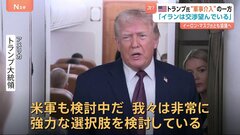物価高だからこそのエシカル・アクションとは
では、消費者が価格を最優先して商品・サービスを選ぶ以上、物価高はエシカル消費と両立しえないのだろうか。答えは「NO」である。もちろん、すべてのエシカル・アクションが物価高と両立できるわけではなく、時代や状況に合う形で消費者に刺さる文脈を作り、長期的観点で浸透・定着させていく工夫は必要である。
日本では、まだ食べられるのに廃棄される、いわゆる「食品ロス」については、2019年に「食品ロス削減推進法」が施行されたこともあり減少傾向にある。しかし、依然として年間472万トンの食品ロスがあり、この量は世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料支援量(2022年で年間480万トン)とほぼ同程度となっている。このうち、約半分の236万トンは外食での食べ残しや商品の売れ残りなどである。
この問題について、2024年12月末に、消費者庁・厚生労働省から「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」が出された。これは、食品ロスを減少させるというエシカルなアクションであるとともに、外食時の食べ残しを持ち帰ることができるという、物価高による生活苦軽減対策にもつながるものといえる。そもそも外食時の食べ残しの持ち帰りは、食品衛生法等で禁止されているものではないものの、腐敗や食中毒のリスク等への懸念や責任の所在の観点から判断が難しいところもある。しかし、ガイドラインの策定でこうしたアクションが推奨されることで、食品ロスが削減できるだけでなく、「食べ物を無駄にしない」というエシカル・マインドが浸透することも期待できる。外食のハードルが下がり、ウェルビーイングが高まる消費者もいるかもしれない。持ち帰りについては、店舗側だけでなく消費者側においても意識高く適切な形で行われることが求められることから、消費者としての責任感や役割意識が醸成されることも期待したい。
また、一部の事業者では、食品ロスを避けるため消費期限が近い商品や規格外商品等にポイントを付与する取り組みを実施している。生活費を抑えてお得に買い物をしたいと考える消費者の間では、「ポイ活」(買い物やサービス利用で付与されるポイントを効果的に貯めて商品購入や支払いに充当するもの)が普及している。値引き商品や見切り品を購入することが、単に節約ではなく「ポイ活」の一環となり、「ケチ・アクション」が「エコ・アクション」に転換されるうえに、「ポイントが溜まる楽しみ」という付加価値もある。溜まったポイントでの消費は、普段買わないものの購入や自分のためのご褒美的な消費に充てるというケースもあるなど、消費におけるメリハリや楽しみを創出する効果もあり、日々のウェルビーイング向上にも寄与するものといえる。
ウェルビーイングを実現する消費とエシカル・アクション
さらに、自らの消費スタイルを見直し、自分にとってより良い商品・サービスへの乗り換えを行うことで、ライフスタイル転換を図る動きもある。こうしたアクションは「換え活」と呼ばれることもある。コロナ禍や物価高騰などを経験し、単なる節約ではなく、自らのウェルビーイングに直結する暮らし方を目指すお金の使い方といってよいだろう。
シェアリングサービスを使用したり、使い捨ての日用品を再利用可能な商品にすることなども、単なる節約や合理性重視の観点だけではなく、自分や社会にとっての付加価値や丁寧な暮らし自体を楽しむ消費スタイルとして捉える人が目立つ。単なる自己犠牲による利他でもなければ、一方的な利己でもない、「社会にもいいし、自分にもいい」というWIN-WINな関係であることがポイントである。
つまり、エシカル消費においては、利他と利己をどう両立させる(ように感じる)かが重要になってくるといえる。「高いけれどエシカルだから買おう」という意識だけでの取り組みでは限界がある。エシカル消費がどの側面で自分の利己となるか、満足をもたらすかという文脈が必要なのである。むろん、地球の未来や将来の自分の暮らしという長期的な利点も、利己ではある。しかし、こうした消費のアクションが即時的・直接的にどう自分のウェルビーイングにつながるのかという観点からのアプローチが、エシカル消費の定着においてもっと考えられるべきであると考える。