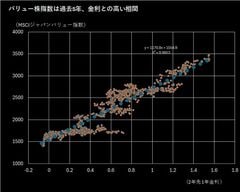人生会議(ACP)普及にあたっての課題
それでは、今後、ACPを普及させていくには、どのような課題があるだろうか。
当然のことながら、本人及び家族等のACPに対する理解が進むことが原則であるが、より重要なことは、ACPにおける丁寧なプロセスを支える医療・介護専門職の態勢において、いかに質と量の両面において確保することができるかであろう。人生の最終段階における医療についての対話は、非常に繊細なものであり、本人が真に望む医療・ケアを対話のなかで引き出すには、これら専門職との信頼関係のうえに初めて成り立つ。例えば、「病院で亡くなりたい」という本人の発言があった場合でも、単に医療サービスが得られるからではなく、家族に迷惑をかけたくないという、思いからの発言である可能性もある。ACPにおいては、真に本人の意思(希望)がどこにあるかを読み取ることが大切だ。このような本人の真意を引き出しながら、医療・介護チームと繰り返し擦り合わせをすることは、追加の負担になることは間違いない。
さらにACPを行うスキルという観点においても、かかりつけ医については、医療技術に加えて、今以上に全人格的に患者と向き合うことが求められ、また人材不足が課題となっている介護専門職にとってもACPを実践する時間と新たなスキルが必要となる。まさに、地域包括ケアシステムにおける医療・介護の多職種連携の真価が問われるともいえるだろう。
加えて、ACPの結果を誰がどのように引き継いでいくのか、という点も気になるところだ。本人の健康状態や時間の経過により、担当する医師、介護担当者、または信頼する家族(あてにしていた配偶者が先に亡くなってしまう等)も変わっていくかもしれない。その場合に、積み上げてきたACPの情報が、救急搬送などで予期せぬ場所に行った場合でも、正しく引き継がれる仕組みを整備する必要もあるだろう。
さいごに
仮にあなたに高齢の両親がいて、ACPに関する項目を確認する場合、改まって「人生会議を始めます」という手続きを踏むのは、親子双方にとっても心理的なハードルは高いだろう。しかし、インフォーマルな会話のなかで、今までの親の生き方、価値観等を踏まえて、さりげなく人生の最終段階に向けた医療・介護の希望を確認していくことはできるだろう。一方、親側の意識としても、自ら主体的にACP項目について、配偶者及び子どもに伝えていく努力も必要だろう。
人生最期の医療・介護に思いを馳せることは、一見すると気の進む作業ではないが、自身の思いを家族に告げ、そして医療・介護従事者と予め意見を擦り合わせることができるとするならば、ACPというそのプロセスは本人及び家族にとっても、プラスの効果をもたらすに違いない。もちろん、本人がACPを望んでいない場合は、無理に行う必要はない。
人の死を通じて引き継がれるのは、金銭などの財産だけではない。死を迎え、本人の最期の瞬間を曝すことにより、遺された者はその生きざまを記憶として引き継ぐことになる。残される家族に対して、財産だけでなく前向きな生き様をメッセージとして、人生会議(ACP)を通じて残せたら良いのではないか。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 社会研究部 取締役 部長 鈴木 寧)