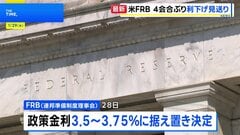気候変動問題が世界中で議論されている。地球温暖化は、ハリケーン、豪雨、海面水位上昇、大規模な干ばつなど、様々な形で地球環境に影響を及ぼしつつある。こうした気候変動リスクへの対応として、洪水保険や火災保険等の活用が考えられる。ただし、気象災害の頻発化、激甚化を受けて、保険の“3つのA” ― アベイラビリティ(Availability)、アフォーダビリティ(Affordability)、アデカシー(Adequacy)に、さまざまな影響が及びつつある。その結果、アメリカでは、リスク対応としての保険活用が制限される事態が増えてきている。気候変動リスクが大きい地域ほど、こうした制限にかかりやすいことから、保険活用の可否によって、リスク格差が拡大する状況も生じている。
アメリカのアクチュアリー会(SOA)は、この問題について議論を進めている。2024年10月には、論点や議論の方向性をまとめたレポート(注記1:“Availability, Affordability, and Adequacy of Insurance in Areas Impacted by Climate-related Risks” Peter J Sousounis著 [SOA Research Institute, Oct 2024] ※以下、単に「レポート」と呼称)が発行されている。本記事では、その内容を見ながら、気候変動問題が保険活用に与える影響について考えてみることとしたい。
保険の“3つのA”
まず、保険が提供する保障を評価する上で重要な要素となる、“3つのA”から見ていこう。
【保険は利用可能性、負担可能性、保障十分性の3つが重要】
一般に、人間社会のリスク管理に保険を役立てるためには、次の3つが機能することが重要とされている。
(1) Availability ― 利用可能性
保険サービスが利用可能であるかどうかを指す。例えば、保険商品が市場に存在するか、その地域で保険加入ができるか、必要な保険へのアクセスが法令や社会制度で担保されているか、といったことを指す。
気候変動問題で言えば、気象災害に対応する火災保険や洪水保険、農業生産への影響を補償する農業保険、熱中症などの病気への備えとなる医療保険などが、利用可能かどうかが問題となる。
(2) Affordability ― 負担可能性
保険料が経済的に支払える範囲内にあるかどうかを指す。例えば、保険料が個人や企業の予算内であるかどうか、個人の収入に対する保険料の割合が過度に高くないか、政府等の補助金や保険料の割引制度があるかどうか、といったことを指す。
気候変動問題で言えば、加入したい火災保険や洪水保険などの保険料が手頃な水準で経済的に支払い可能かどうかが問われる。
(3) Adequacy ― 保障十分性
保険が提供する保障の内容が被保険者のニーズに対して十分かどうかを指す。例えば、保険金の支払額が災害による損害や病気・ケガによる医療費を十分にカバーするか、保障範囲は想定されるリスクに対して適切か、保険契約条件(免責額、支払限度額等)が妥当か、といったことが該当する。
気候変動問題で言えば、住宅保険の風水災補償で洪水時の浸水被害は保険金で十分にカバーできるか、補償の対象外となる災害が多くはないかといった点がこれに相当する。
これらの要素がバランスよく機能することで、保険制度が効果的に社会のリスク管理をサポートすることとなる。