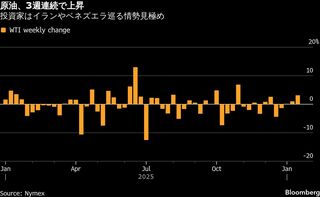新しいインフレ局面における春闘の意義
(1)2025年春季労使交渉のテーマ
以上みてきたことを要すれば、実質賃金の持続的上昇を伴う賃金・物価の好循環はなお道半ばであるが、名目賃金の持続的な引き上げの気運が広がってきたことは前向きに評価できる。望ましい春季賃上げ率を「定期昇給分+望ましいインフレ率+生産性向上トレンド」と考えれば、「5%程度(=2%弱+2%弱+1%半ば)」が中長期的に妥当な数字になる。もっとも、1990 年代の前半ごろまでの年功賃金制度が健在であった頃から賃金構造・就業構造が大きく変わり、春闘賃上げ率と平均賃金の上昇率の乖離が大きくなっている。
ただし、春闘賃上げ率は企業の賃上げ方針を示すものであり、過去からの連続性を見る意味で引き続き必要性ある。一方で、マクロ的な重要な平均賃上げ率とは乖離があるため、従来の賃上げ率に加え、「従業員一人当たり平均賃金の上昇率」の2本立てによって労使間で交渉し、それらのデータを開示していくようにしていくべきであろう。
賃金構造の個別化により、単なる賃上げ率のみならず賃上げ原資の分配ルールについても労使が話し合っていくことが重要になる。その点を踏まえ、今後の賃上げの基本的な方向性を示せば、以下の通りになろう。
【大手企業における2024年並み賃上げ率の維持】
すでに指摘したとおり、今後のバランスのとれた経済・物価状況を勘案すれば、春季賃上げ率は5%程度が望ましい。その意味で、大手企業については2024年並みの賃上げ率を中期的に定着させることが重要である。
【取引価格適正化による企業間での付加価値の再配分と中小企業賃上げ率の引き上げ】
中小企業の賃上げ率も高まってきているものの、5%には届かず、2025年は一段の高まりが望まれる。ただし、いわゆる「防衛的賃上げ」が目立つなか、収益体質の改善が求められる。その際、個々の中小企業がそれぞれの付加価値創出力を高める努力を個々に行うことを必要条件として、コスト増の価格転嫁が適正に進む環境作りを全体で進めることが重要である。大手企業の労働分配率が大きく低下していることを踏まえれば、仕入れ価格や委託価格を引き上げ、大企業セクターから中小企業セクターに付加価値を再配分していくという発想が求められる。
【女性の登用促進と平均賃金の引き上げ(男女賃金格差縮小)】
労働者の属性別グループでいえば、女性の平均賃金が低いことが日本の問題であり、国際的に見て問題になっている性別賃金格差を是正する形で、女性の賃金の引き上げに取り組むことが必要である。もちろん、それは女性能力の一段の活用と相まって持続的な引き上げにつながるのであり、管理職や重要ポストへの女性登用と性別役割分担の見直しの前提となる男性の働き方改革も、同時に進めることが求められる。
【賃金カーブの適正化と雇用延長による生涯賃金拡大】
労働者の属性別グループでもう一つのターゲットは高齢者である。大手企業では中高年賃金が伸び悩んでいることを確認したが、これは脱年功を進めるという意味では必要な動きといえる。問題は、60歳以降の賃金が非連続的に低下することである。人口構成からみて、シニア活躍こそが労働力不足対策・消費活性策・社会保障財政健全化策といった多角的な面から重要となるなか、60歳以上の賃金水準の維持、その前提としてミドル・シニアへの積極的な能力開発投資が極めて重要である。
(2)社会改革推進の場としての新春闘の構築
以上、2025年春闘で労使が追求すべき具体的なテーマ4点を指摘したが、それは実質賃金の持続的向上のいわば必要条件にとどまる。なぜなら、実質賃金を考える場合、交易条件を考慮する必要があり、それは産業構造・エネルギー構造に関わる問題だからである。産業・エネルギー構造の転換は、政府の関与が不可欠である一方、その主役は個々の企業、個々の労使である。こうしてみれば、このところ政労使会議が復活する動きは望ましいものといえるが、それが単に賃上げ機運の醸成の場にとどまっていては不十分である。付加価値分配構造、産業・エネルギー構造の社会全体での変革にトータルで取り組むには、何よりも労使が協力した主体的な取り組みが不可欠といえ、それを政府が強力にバックアップする体制整備が必要である。それには公労使・産官学が連携する体制整備が不可欠で、春闘をそのための社会改革推進の場に昇華させていくべきである。
具体的な仕掛けとしては、①独立委員会、②中央政労使会議、③地域別連携協議会の3点セットの実現を提案したい。
①独立委員会の設置(目指すべき中長期的な賃上げ率やその前提となる経済政策のビジョンを策定)
…超党派で人選を行い、政労使三者から一目置かれる経済学者の重鎮を委員長として、労使の代表者を含む10名程度の委員会を組成する。事務局を有し、経済成長・産業構造・エネルギー構造・分配構想等、多角的な観点からの経済・労働市場の分析を前提に、ビジョンをまとめ上げる。
②中央政労使会議の定期開催
…上記の独立委員会の提示したビジョンを承認したうえで、四半期に1回の定期開催により、実現に向けて必要な政策を議論し、大きな政策の方向を決める。
③地域別の連携協議会の設置
…中央政労使会議の方針の実現にむけて、都道府県単位で労・使、官、学の代表が集まり、地域の実情にあった政策を議論する。必要に応じて分科会を設け、地域を挙げての生産性向上策や産学連携の在り方について具体的な施策を作り込む。
(3)2つの重点施策
以上の3点セットは仕掛けづくりの提案であり、改革プロセスを前に進めるには、具体的な目標とそれを実現するための公労使・産官学連携の姿を明示することも重要である。この点で2つの重点施策を提案したい。
<特定最低賃金制度の積極活用>
一つ目は、特定最低賃金制度の積極活用である。特定最低賃金は、特定地域の特定産業の一定割合の労使が合意すれば、地域別最低賃金を上回る水準に最低賃金を独自に設定できる仕組みである。これまでは使用者サイドが慎重姿勢を示してきたが、人手不足が深刻になるなか、特定最低賃金の引き上げに取り組むことは地域の産業の人手確保策として有効な状況が生まれている。その際、地域全体でのブランドづくりや企業横断的な人材育成の仕組みづくりに取り組むことで、地域産業のパイを増やして賃金引き上げを持続的なものとすることが可能になる。政策的には、特定最低賃金で大幅賃上げを目指す場合、国内外を見据えたブランディング戦略・デジタル投資・人材育成策等とセットにして地場産業が面的な生産性向上を図れるような支援をすべきであろう。
<エッセンシャル部門の賃上げ・生産性向上集中支援策>
もう一つは、エッセンシャル部門の賃上げ・生産性向上集中支援策である。「令和のルイスの転換点」を超え、絶対的な労働力不足局面に入るなか、経済社会活動の不可欠な基盤である「エッセンシャル部門」の労働力不足が深刻化している。一方、「オフィス部門」の労働力は余剰気味なのが実情である。この背景には「AI(人工知能)によるホワイトカラー労働の縮小」と「高齢化・高学歴化等による現場労働の不足」という2つの現象が同時進行しているという構図がある。とりわけ米国では、かつてオフィス専門職の賃金伸び率が高かったが、近年は鈍化し、むしろ現場系職種の賃金の伸び率の方が高くなっている。わが国ではまだ明確化していないが、予想される今後の労働力人口の減少スピードを勘案すると、影響は一段と大きい。ホワイトカラーの余剰と現場労働の不足のミスマッチ拡大で、ミクロの生産性向上はみられても、ミスマッチ失業が増加してマクロ経済が低迷する恐れがある。そうしたシナリオを避けるには、現場労働に魅力的な雇用の受け皿を作る必要がある。
具体的には「アドバンスト・エッセンシャルワーカー(AEW:高賃金な高度現場人材)」を政労使・産官学が連携して創出することに突破口がある。それは、AIやロボティクスの技術を結集し、人と技術の新しい協業による高生産性・高賃金の現場職種を意味する。日本の強みである現場力・品質力を活かす道であり、AIによるホワイトカラー余剰労働力の受け皿になることで、ホワイトカラー部門の飛躍的な生産性向上を円滑に進めることにも寄与する。こうした取り組みを政府が強力にバックアップする形で、すでに開始されている民間企業の取り組みをパイロットプロジェクトとして推進することが重要であろう。
(※情報提供、記事執筆:日本総合研究所 調査部 客員研究員 山田 久)