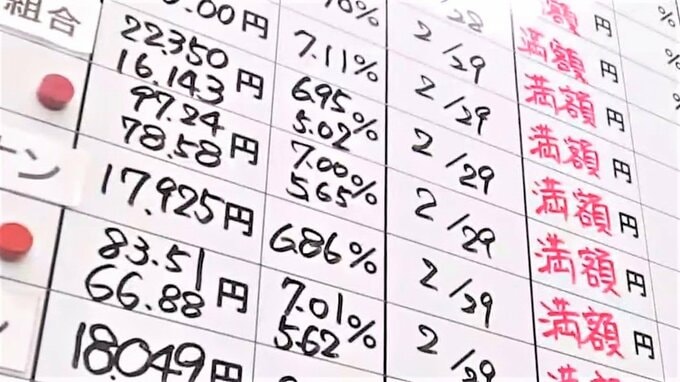2025年春季労使交渉に向けた動きが始動している。連合は「2025春季生活闘争方針」として、「全体の賃上げの目安は、賃上げ分3%以上、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含め5%以上とし、その実現をめざす」「賃金実態が把握できないなどの事情がある中小労組は、上記目標値に格差是正分1%以上を加えた 18,000円以上・6%以上を目安とする」ことを確定した(2024年11月28 日)。30年余りぶりの高率賃上げとなった2024年春闘の定着・拡大を目指す方針だが、財界の首脳も理解を示している。十倉経団連会長は「2023年は賃金引上げの力強いモメンタム『起点』の年となり、2024年はそれが大きく『加速』した年となった。2025年はこの流れを『定着』させ、2%程度の適度な物価上昇のもと、賃金と物価の好循環を実現したい」と述べている(2024.10.22定例記者会見での発言)。
総選挙を経て発足した石破内閣も、前・岸田内閣の方針を引き継ぎ、賃上げ推進に積極姿勢を示し、昨年11月26日に「政労使会議」を開催し、大幅な賃上げへの協力を呼び掛けた。このように賃上げは政労使間の合意事項になり、名目賃金の上昇率は着実に高まっている。しかし、国民生活水準の向上という目標に不可欠な「実質賃金の持続的上昇」については、なお不透明な状況にある。本レポートでは、2024年春闘での賃上げが大幅になった背景とその実態を分析したうえで、実質賃金の持続的上昇に何が必要かを検討する。それを踏まえ、経済・物価動向が新たな局面に入ったとみられる今、春闘にどういった役割が期待されるかについて考える。
2024春闘・大幅賃上げの背景と内実
(1)大幅賃上げの背景
2024年を振り返っておくと、春季賃上げ率は経団連・連合・厚生労働省集計のいずれの指標をみても5%を上回った。バブル崩壊前以来33年ぶりの高さとなった形だが、この背景には何があったのか。今後の持続性を判断するには、ここ数年の流れの中でとらえることが重要である。
実は、数年前からグローバルに事業を展開する大手企業の経営者の間では、賃上げの必要性は認識され始めていた。それは、日本はもはや高賃金国ではないという事実への気づきであり、これが第1の要因である。OECDの調べでは、購買力平価ベースの日本の実質平均賃金は2018年以降韓国を下回るようになり、2022年以降の円安局面で「安いニッポン」が実感され、経営者間で危機感が共有されていった。象徴的なのはユニクロを展開するファースト・リテイリング社が、2023年に年収で最大約40%の賃上げに踏み切ったことである。その背景として同社CFOの岡崎氏は「世界で通用する働き方ができる人材に対し、成長できる機会を提供すると同時に報酬でも報いていく」と語っている。
第2の要因としては、コロナ禍やウクライナ戦争を経て、数年前のデフレ経済から緩やかなインフレ経済に移行したことを指摘する必要がある。民主主義対権威主義の対立が先鋭化し、グローバル経済は経済効率よりも安全保障を優先する局面に入り、世界貿易の伸びが鈍化している。地球温暖化問題が深刻化するなか、干ばつや洪水、家畜の疫病流行などの相次ぐ自然災害が食糧供給減をもたらし、脱炭素に向けたエネルギー転換への取り組みが、跛行性を持ちながらも一次産品コストを押し上げている。こうして、グローバルなコスト体系が上方シフトするなか、日本国内の要因にも物価押し上げファクターが生まれている。一つには、円相場が円安方向に振れやすくなったことがある。これは大幅な内外金利差の存在があるが、貿易収支の基調が赤字化したことも無視できない。もう一つは労働力不足が新たな局面に入ったことで、労働集約的である個人向けサービス価格を持続的に押し上げ圧力が生じるようになったことが大きい。
女性の年齢別労働力率がほぼ米国を上回るようになり、65歳以上のシニアの労働力率の上昇トレンドが一巡するなか、2010年代半ば以降の労働力人口の増加トレンドに頭打ち感がみられている。それ以上に、ここ10年で伸びてきた女性やシニアの限界労働力は短時間労働者が主で、労働投入量(マンアワー)ベースではすでにピーク対比大幅に水準が落ち込んでいることが見逃せない。外国人の受け入れの余地はあるが、円安進行により日本で働くことの魅力は落ちており、過度な期待はできない。結果、女性・シニア・外国人の労働力を頼っていた飲食・宿泊、個人向けサービスなどの物価には、コストプッシュ・インフレ圧力が恒常的に働くようになっている。
そして第3に、人手不足が深刻化するなか、人材確保のために賃上げに踏み切る企業が増加している。とりわけ、2024年春闘では、転職志向が高まる若手社員のつなぎ止めや新卒獲得のアピールのため、「賃上げ競争」の様相が呈した。注目されるのは、従業員1000人以上の大手企業の大卒・大学院卒社員の 30歳代前半の平均給与は、転職者が非転職者を上回るようになっていることである 。そうしたなか、獲得競争が激化する若手社員を確保するため、新卒初任給を引き上げ、それによる2年目・3年目社員との給与水準の逆転を回避するためにも、若手・中堅の賃上げに前向きになっている。たとえば、月額3万5000円という驚異的な高さで回答した日本製鉄は、「国内製造業トップクラス、すなわち一流の処遇」を確保し、それに「相応しい一流の実力をつけて、生産性向上」を実現することを理由に挙げている。希少化する人材を確保し、希少ゆえに各人の質を高めることが企業成長に不可欠であるとの認識が広がっている。