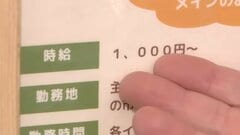(ブルームバーグ):米連邦準備制度理事会(FRB)が来年実施する定期的な金融政策の枠組み見直しは、世界に影響を及ぼすものとなるだろう。FRBは正しい取り組みに注力する方針だが、重要な部分が抜け落ちているようだ。
明るい材料としては、FRBはゼロ金利制約によって短期金利がゼロ近辺に張り付かないよう目指した制度を廃止する構えのようだ。2008年の金融危機と新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)によるゼロ金利の経験を経て、20年の枠組み見直しで導入されたこの制度では、FRBは一定の条件下でゼロ金利の維持にコミットした。
だたこの戦略は、コロナ禍を脱した経済にとってはそぐわなかった。22年3月時点でも金利は依然としてゼロ近辺で、FRBは長期金利の引き下げを目的に米国債や住宅ローン担保証券の買い入れを継続していた。一方で失業率は3.8%となり、FRBが重視するインフレ率は5%を超えていた。米金融当局は、経済が過熱しているにもかかわらず、異例の景気刺激策を実施していた。
パウエルFRB議長は問題を認識しているようだ。パウエル氏は中立金利が08年の金融危機後の10年間よりも高くなっているため、ゼロ金利制約のリスクは低下している可能性が高いと指摘。同氏は「オーバーシュートを目標にするのではなく、インフレを目標にする」と述べている。
ここまでは順調だ。しかし、枠組み見直しの議題には含まれていないと思われる重要な問題が3つある。
1つ目は、FRBに量的緩和(QE)の枠組みが必要な点だ。QEとは、追加の景気刺激策としてFRBがこれまで実施してきた資産購入策(およびその反転策として知られる量的引き締め)である。枠組みがなければ、市場参加者は金融政策がいつどのように実施されるのか理解することは困難になる。市場の期待は、長期金利や金融情勢、経済への金融政策の伝達に影響を与えるため、政策の有効性が損なわれることになる。
2つ目は、実際に何をすべきかをよく理解するために、量的施策の費用対効果を評価する仕組みが必要だということ。例えば22年3月に終了した資産購入プログラムの最後の1年について考えてみよう。コロナワクチン開発とバイデン米政権による大規模な財政刺激策によって、追加での金融刺激策が不要だったことはほぼ明らかであったにもかかわらず、FRBは1兆4000億ドル(約209兆円)の資産を購入した。これらの購入により、米国の納税者は最終的に1000億ドル余りの負担を強いられることになる。コロナ禍での量的緩和の総費用は5000億ドルに達する可能性がある。
3つ目は、FRBは金利ターゲットを変更する必要があるということだ。銀行の準備金が潤沢にある中で、銀行がほとんど利用しなくなった市場を追跡するフェデラルファンド(FF)金利は時代遅れである。FRBは銀行が中央銀行に保有する準備金に対する金利に切り替えるべきだった。今になってようやく、という感もあるが。
また、検討しなくてもいい問題も1つある。ゼロ金利制約にとどまるリスクを低減するために、FRBはインフレ目標を2%超に引き上げるべきかどうかという問題だ。パウエル氏が指摘したように、そのリスクは後退している。さらに重要なのは、インフレが急騰した時期でも2%という目標がインフレ期待を適切に維持するのに役立ったことだ。目標値を変更することはFRBの決意に対する信頼を弱める恐れがある。
米大統領選で、ドナルド・トランプ氏がカマラ・ハリス氏に勝利したことは、有権者がインフレを本当に好まないことを示している。有権者の意思は、何らかの形で考慮されるべきである。
(ニューヨーク連銀の前総裁、ウィリアム・ダドリー氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。このコラムの内容は、必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:The Fed’s Next Big Policy Rethink Needs Rethinking: Bill Dudley
(抜粋)
翻訳コラムに関する翻訳者への問い合わせ先:ロンドン 楽山麻理子 mrakuyama@bloomberg.netコラムニストに関する記者への問い合わせ先:New York William C Dudley “Bill” wdudley3@bloomberg.netコラムについてのエディターへの問い合わせ先:Mark Whitehouse mwhitehouse1@bloomberg.netもっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2024 Bloomberg L.P.