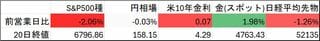インフレは順調に低下しているという評価で、警戒しているのは「複数(a couple)」だけ
利下げの判断に重要なインフレについては、順調に低下しているという見方が多かった。現状の評価については、「ほぼ全ての参加者(almost all participants)は、前月比の動きは引き続き不安定であるものの、今後発表されるデータは概ね持続的に2%へとインフレ率が戻るという見通しと一致していると判断した」とされた。見通しについても、「参加者(some participants)は、インフレ率が2%に向けて持続的に推移しているとの確信を維持していると指摘した」とされた。一方、「そのプロセスが以前に予想されていたよりも長引く可能性を指摘する参加者も複数(a couple)いた」とされたが、警戒感を持っているのが「複数(a couple)」ということであれば、多数派になる可能性は低いだろう。
なお、今回のFOMC(11月7-8日)は大統領選(11月5日)の直後に行われたが、トランプ氏の政策(関税や減税)を予測して見通しに反映させるような議論はなかった。この点については、バーキン総裁がFT紙のインタビューで答えた「実際に起こる前に解決しようとしてはいけない」というスタンスが共有されているのだろう。市場では「関税=インフレ加速」と捉えられることが多いが、関税によって経済活動が停滞する可能性などを考慮すると、インフレ的なのかディスインフレ的なのかは微妙なところである。現在の政策金利が中立金利より高い状態にあることに鑑みると、先行き見通しが不確実であればあるほど中立金利に近いところで政策金利を「待機」させたいと考えるのが自然であると、筆者はみている。FRBが中立金利付近まで利下げを進めたいという意思はかなり強いように思われる。
経済活動の上振れもインフレ鈍化を示すという超ハト派の意見も
経済活動の上振れについても、やや驚くほどハト派的なロジックが示された。具体的には「一部の参加者(a few participants)は、最近の力強い実質GDPの増加が好ましい供給面の展開を反映したものである限り、経済活動の強さがインフレ圧力の上昇要因となる可能性は低いと指摘した」とされた。「一部の参加者(a few participants)」は多数派と言えるほど多いわけではないが、最近の経済活動の活性化は供給側の回復に依存するもので、インフレ的ではないという解釈は非常にハト派的である。確かに、これまでインフレ圧力が強かった(需要>供給)ことで、GDPの達成水準が「供給」で決まっていたとすれば、供給力が強化されて均衡状態(需要=供給)になる過程でGDPの達成水準が持ち上がるというロジックは通る。
むろん、この考え自体は足元の経済活動の上振れを都合良く解釈しているようにもみえる。しかし、逆に言えばやや都合の良い解釈を持ち出したとしても、利下げサイクルを続けていきたいという考えがあるのだろう。FRBが中立金利まで利下げを進めていく意思は、想定以上に強いのかもしれない。
長期金利の上昇はインフレ予想の引き上がりを示さないと、スタッフが説明
パウエル議長は11月FOMC後の記者会見で最近の金利上昇について問われ、「債券利回りの上昇は我々も注視しているが、1年前の水準にはほど遠い」と述べていた。債券市場が織り込むインフレ予想についても「もし我々が、長期的なインフレ期待がより高い水準で固定化していると見たら、我々は懸念するだろう。我々が見ているのはそういう状況ではない」と、懸念を示さなかった。この点について議事要旨でFOMCメンバーが議論している様子はなかった。
しかし、この点についてスタッフ(事務方)からは「長期金利の上昇は主に期間プレミアムの上昇によるものと考えられ、これは投資家がリスクのバランスを、実質GDP成長率の鈍化とインフレ率の低下を特徴とする結果から離れてシフトさせているという見方と一致している。市場ベースのインフレ補償の指標(インフレ予想)は、比較的低い水準から上昇したが、調査に基づく長期インフレ期待の指標はほとんど変化がなかった。これらの指標は、インフレ率が徐々にFRBの2%という目標に近づいていくという見通しを示し続けている」という説明があった。すなわち、長期金利の上昇はリスクプレミアムが主導しており、投資家が経済見通しを引き上げたり、インフレ予想を引き上げたりしている訳ではないという整理である。言い換えると、不確実性が高まる中で投資家が金利リスクを取る動きを避ける中で結果的に長期金利が上昇している(経済・物価見通しが変わった訳ではない)という解釈になっており、FRBがインフレ予想の上昇を懸念する状況ではなさそうである。
(※情報提供、記事執筆:大和証券 チーフエコノミスト 末廣徹)