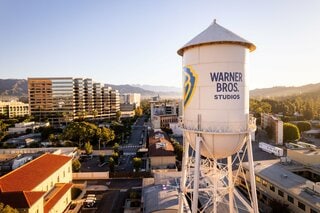記事のポイント
・利下げ継続が基本路線という姿勢が示された
・経済活動が上振れてもインフレが高止まりしなければ、利下げ継続へ
・インフレは順調に低下、警戒しているのは「複数(a couple)」だけ
・経済活動の上振れもインフレ鈍化を示すという「超ハト派」の意見も
・長期金利上昇はインフレ予想引き上がりを示さないと、スタッフが説明
利下げ継続が基本路線という姿勢が示された
FRBは11月26日、FOMC(11月6-7日)の議事要旨を公表した。11月FOMCでは、市場予想通り25bpの利下げが決まった(FF金利誘導目標は4.50-4.75%)。パウエル議長は「時間をかけてより中立的な水準まで引き下げるというプロセスにある」(筆者訳。以下同)と、利下げが続いていくことを示唆したが、具体的な発言はほとんどなかった。
議事要旨によると「すべての参加者は、FF金利の誘導目標を25bp引き下げ、4.50%から4.75%とすることが適切であると判断した」「参加者は、金融政策のスタンスをこのようにさらに調整することは、インフレのさらなる鈍化を可能にしながら、経済と労働市場の強さを維持するのに役立つと指摘した」とされ、順当に25bpの利下げが決まったことが分かった。
今後の利下げのペースについては「参加者は、インフレ率が持続的に2%に向かって低下し続け、経済がほぼ完全雇用に近い状態を維持するという想定通りのデータが得られた場合、時間をかけてより中立的な政策スタンスへと徐々に移行することが適切である可能性が高いと予想した」とされた。「時間をかけて」とされたことから、いずれかのタイミングで利下げペースの減速が決まる可能性が高いものの、次回(12月)のFOMCで減速(利下げスキップ)が必要であるという切迫感は全くなかった。12月FOMCでは再び25bpの利下げが決まる可能性が高い。今回のFOMC議事要旨はハト派的だったと言えるだろう。FF金利先物市場では、12月の利下げ確率が63.1%となっている。前日(25日)は55.9%だったことから、やや確率が高まった。
経済活動が上振れてもインフレが高止まりしなければ、利下げ継続へ
今回の議事要旨で最も重要な記述だと筆者が考えたのが、「一部の参加者(some participants)は、インフレ率が高止まりする場合には、委員会は政策金利の引き下げを一時停止し、引き締め的な水準に維持することも可能であると指摘した。また、労働市場が悪化したり、経済活動が低迷したりした場合には、金融緩和を加速させることも可能であるとの意見もあった」という部分である。すなわち、利下げするか停止するかの判断はインフレ動向で決まり、利下げ(金融緩和)の程度の判断は経済活動によって決まる、ということである。足元では経済活動が上振れしているが、そのことをもってして利下げを減速することはあっても利下げを停止することはない、ということである。この論調はバーキン・リッチモンド地区連銀総裁がFT紙のインタビュー記事(11月21日)で「インフレ率が目標値を上回る状態が続いているなら金利引き下げには慎重になるべきだ。一方、失業率が上昇してきている場合は、より積極的な姿勢を取るべきだ」(筆者訳)としたことと一致している。FOMC内で共有されている可能性が高い。