豊かな海を守ろうと企画された丼ぶりメニューがあります。素材は富山湾の深海魚です。
おいしそうな天丼。さらには味噌汁。実はこれ、すべて深海魚で作られたものなんです。
天然のいけすとも呼ばれる富山湾。春にはホタルイカ、秋にはベニズワイガニなどおよそ500種類もの魚がとれる日本有数の漁場です。しかし、その一方で市場に出回ることのない魚も―。
漁を終えた漁師が海に捨てているのは▼サイズが規格外、▼水揚げ量が少ないなどの理由で売り物にならない「未利用魚」です。
この魚は「ヤマトコブシカジカ」という深海魚で魚津では「ミズガンコ」と呼ばれています。
底引き網漁で甘エビなどと一緒に取れますが漁獲量も少なく、そのグロテスクな見た目から敬遠され、廃棄されてきました。またミズガンコは水分が多いため調理がしにくく、他にもおいしい魚が水揚げされる富山県魚津市では、いままで食材としての選択肢から外れていました。
魚津漁業協同組合 濱住博之組合長:
「海にポイポイポイポイ捨てられていちゃ、あまりにもかわいそうだなと。貴重な食料として生かすべきじゃないかなと」
海洋資源の有効利用や漁業者の収入向上を目的に去年、魚津市と魚津漁協が未利用魚の活用推進に動き始めました。富山県内には成功事例があります。それが今ではお馴染みとなったゲンゲです。
冷蔵技術や交通網が発達していなかった頃、足が早いゲンゲは市場に出回ることなく浜に捨てられていたといいます。漁師の間では「下(げ)の下(げ)の魚」として扱われ、それがゲンゲの名前の由来となっています。
しかし近年、流通が発達し新鮮なまま天ぷらや唐揚げとして提供されはじめると、そのおいしさから滅多に出会うことのできない幻の魚「幻魚(げんげ)」と呼ばれ、観光客を中心に人気を集めています。
魚津漁業協同組合 濱住博之組合長:
「第2のゲンゲ。幻の魚がまた増えるということ…」
長年、日の目を見ることのなかった魚津のミズガンコ。第2のゲンゲを目指していざ商品化へ。去年10月、まずは味噌汁の具材として活用してみました。
魚津漁業協同組合 濱住博之組合長:
「水分が多い魚かなと思っていましたけど、身もしっかりしています。おいしいです」
そしてことし、未利用魚の可能性をさらに広げようと市内の飲食店にも協力を依頼、深海魚を使った丼ぶりメニューを市内7か所で販売する「とやま湾の幸魚津丼フェア」を開催することになりました。
全国のトップニュース
【速報】高市内閣支持率78.1% 先月調査から2.3ポイント上昇 JNN世論調査

各地で“冬の嵐” 関東では山火事相次ぐ あすも日本海側などで突風や大雪に警戒
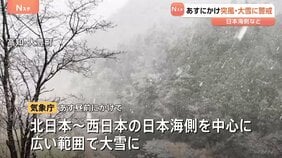
【大雪警報】今夜が最大の山場 JPCZ停滞で東北80cm・北陸東海70cm予想 13日(火)に「第2波」襲来か 雨雪シミュレーション

死亡女性は“オブザーバー”か 移民当局の取り締まりを監視する活動に参加 米ミネソタICE職員発砲事件

毎年恒例「ド派手」衣装でお祝い 北九州市で二十歳の記念式典

【壁の中に女性遺体】年始の営業で空気清浄機が4~5台、客が感じた異変「なんかすごく暗いね」死体遺棄容疑の49歳男、遺体の死因は窒息死と判明

山梨・上野原市の山林火災 発生4日目も鎮圧のめど立たず 火元は登山道の休憩スペース周辺か

小泉大臣も跳んだ! 陸自の新年恒例「降下訓練始め」 過去最多の14か国が参加



