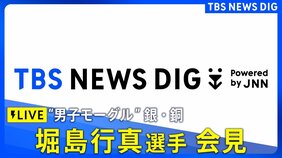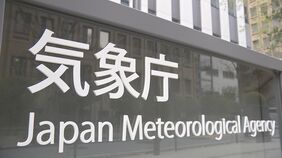沖縄県内の児童が、宮崎県で戦時中の学童疎開を追体験する取り組み。当時、沖縄から300世帯が疎開した「リトル沖縄」と呼ばれる地域で、現地の児童と交流する様子などをお伝えします。
宮崎の「リトル沖縄」が守ってきた伝統と文化
宮崎県を訪れた10人の児童。3日間、親元を離れて当時の学童疎開を追体験します。
対馬丸記念館 堀切香鈴学芸員
「手を合わせてください。いただきます」

初日のお昼ご飯。3日間の食事は当時を再現した「やーさん飯」です。
Q味はどう?
児童「おいしい。特にお味噌汁とかがおいしい」
Qこれを3日間ってそんなに苦じゃない?
児童「うん」
初めてのやーさん飯には、意外と満足できたようです。
昼食のあと向かったのは、当時、沖縄からおよそ300世帯が疎開した、宮崎市の波島地区。今も沖縄の文化が色濃く残るこの地域は、「リトル沖縄」と呼ばれています。

ここでは、地元の宮崎東小学校の児童と一緒に、語り部の常盤泰代さんから、沖縄と波島地区の関わりを学びます。
宮崎県の語り 部常盤泰代さん
「自分と同じ名前(苗字)がいくつあるでしょう」
児童たち
「比嘉はいっぱいある。城間とか、中村」

波島地区に疎開した人達の一部は、戦後もこの地にとどまり、80年もの間、遠く離れた場所で、沖縄の伝統と文化を守り続けてきました。
宮崎県の語り 部常盤泰代さん
「宮崎東小学校では、エイサーを全校児童で踊っています。80年近くここに住んでいる、1世から4世、小学生が4世ですよ。4世になっても、この沖縄の文化を忘れることは無かった。守らなければいけない故郷の文化を、ずーっとこの何十年も守ってこられました。(みんなに)できる?何が必要?」
仲宗根愛美さん(小5)
「『この地域にあるこれはすごいんだぞ』っていう誇らしさを持つこと」
同じルーツを持つ児童たちが、世代を超えて交流を深め、何を感じたのでしょうか。
高橋永さん(小6・沖縄)
「沖縄と宮崎でつながっているところも多いし、交流がたくさんあるから、これからも大切にしていきたいなって思いました」
名城遥香さん(小5・宮﨑)
「おばあちゃんが沖縄に住んでいた。疎開したところで、沖縄の文化を広めていって、宮崎東小学校にエイサーとかを作ってきてくれたから、すごいなって思った」
波島地区の皆さんに別れを告げて、児童たちは宿へと向かいます。

当然、夕食もやーさん飯。食後には、こんな本音が…。
大濱梨乃さん(小6)
「やーさん飯、おいしかったけど味薄かった」
神谷美心さん(小5)
「ずっと同じ具材とか料理とか出されても、味も変わらないからさ」
大濱梨乃さん(小6)
「仕方ないのかなってのもあるけど、やっぱ恋しくなる、自分の家のご飯が」
こうして、初日の夜は更けていきました。