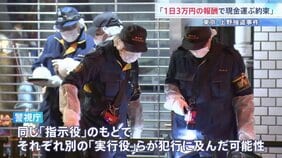▽学校で起こる事件・事故に詳しい 大貫隆志さん
「あまり(従来と)代わり映えしない内容かなという印象を受けました。(県の再発防止策は)研修しましょうとか、そういった類の教員側の意識改革というもの。なぜそれがだめなのかというと、今までずっとやってきたからなんです。ずっとやってきて見逃してしまった、許してしまった」
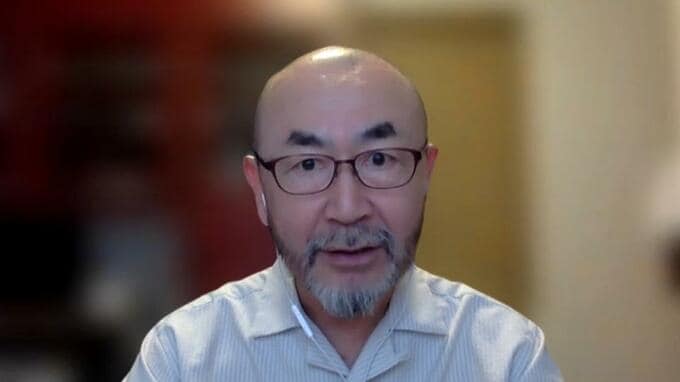
「具体的に言えば、学校の外側に、教育委員会の外側に相談窓口がなければいけない」
新たな機関をつくる動きがある地域も
沖縄以外では、学校でのハラスメントを根絶するための新たな機関を作る動きが出始めている。
熊本市では2020年度から、保護者らから相談のあった教職員の行為については、教育委員会の「学校問題対応チーム」が調査。
体罰や暴言などにあたるかの認定は、弁護士や医師、保護者などの外部の有識者で構成される「体罰等審議会」が行っている。

▽熊本市教育委員会 学校問題対応チーム・橋爪富二雄 教育審議員
「それまでは学校独自で対応していた。初期対応は全部学校がやりますということで、(教育委員会に)数として上がってくるのは非常に少なかった」
「でも本当は体罰暴言はもっとあるんじゃないかというような疑念というか、実態をもっと知った方がいいんじゃないかと」
体罰等審議会に相談したい保護者や子どもたちは、「子どもを守る相談票」を記入し、学校か教育委員会に提出。提出されたものは全て審議される。
2023年度までの4年間で審議された事案は382件そのうち、体罰が20件、暴言等が51件、不適切な行為が91件認定された。体罰や暴言と認定された事案は、報道機関に公表される。
▽熊本市教育委員会 学校問題対応チーム・橋爪富二雄 教育審議員
「学校、っていうのはちょっと違った世界があって、保護者の方も、例えば学校の先生にお世話になっているので、そういうのを言えない、言いづらい、でもすごくストレスを抱えている。そういう文化がある。そこに目をつぶったり触れないまま置いていても、本当の教育の質は上がらない」
事案の調査にあたるメンバーの1人、橋爪富二雄さんは元教員。審議会ができる以前から、教育委員会の立場で調査を行ってきた経験がある。
そんな橋爪さんでも、外部の第三者の目が入り、これまでの調査の甘さを痛感したという。

「中には調査の資料不足ということで、却下されるときもあります。これとこれについて調べて資料にしてもらわないと認定ができません、と(審議が)持ち越しになります。何回もありました」
「(事案の中には)“走らされた”というのもある。その場合は、例えば山道の傾斜の角度を何か所も測ります。今はありとあらゆる手段を使って調査し、資料にし、映像・音声も全部提出して認定をいただいていますので、調査をした内容の深さと広さは全然違います」