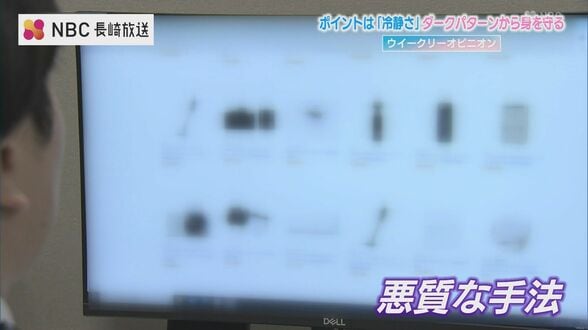今回は長崎県が誇る農林水産物に関するテーマです。
いま日本国内から海外へ輸出される農林水産物や食品の輸出額は10年連続で過去最高を更新し続けています。
長崎の“暮らしと経済”を分かりやすくお伝えしている『ウイークリーオピニオン』平家達史NBC論説委員とお伝えします。
農林水産物の輸出急増中!長崎県の主力品目は
【平】農林水産省によりますと、2022年の農林水産物や食品の輸出額は、2021年より1,766億円増えて 過去最高の1兆4,148億円でした。
10年連続で過去最高を更新し、1兆円を超えるのは2年連続です。
海外では多くの国で新型コロナの感染拡大が落ち着き、外食需要が回復したことなどに加え、急速に進んだ円安が輸出の追い風になった形です。
公表されている品目をみてみると、特に輸出額が多い品目が──

ホタテ貝の910億円、ウィスキーの560億円、牛肉の520億円がトップ3です。
それにソースなどや、清涼飲料水、日本酒が続きます。
『水産物』ではホタテに続いてブリが2位の362億円。
『野菜・果樹等』では、りんごが187億円でトップです。
増え続けている農林水産物や食品ですが、2022年は前年比で14.3%増加しており、なかでも水産物は3割弱増加しています。
政府は農林水産物と食品の輸出について、2025年までに2兆円の達成を目指すとしています。
【住吉 光キャスター】2年後には2兆円ですか。それだけの伸びが期待されているとなると、『長崎県はその波に乗れているのか』というのが気になりますね。
【平】そうですね。いまご紹介した輸出額は、日本国内全体を対象としたデータで、都道府県別の統計はありませんので、長崎県内の農水産物の輸出額は県や税関などがまとめた数字が主な指標となります。
このうち農産物の輸出額については、生産者や県内自治体などでつくる「輸出協議会」を通じて県がまとめていて、その数字がこちらです。

2014年度の調査開始以降、ほぼ右肩上がりで推移していて、直近の2021年度の輸出額は6億2,000万円に上っています。
【住】長崎県内には美味しい農産物がたくさんありますが、輸出が伸びているのはどんな品目になるんでしょうか。
【平】県の農産加工流通課によりますと、特に輸出が好調なのがイチゴ、牛肉、そして鶏卵となっています。
中でもイチゴの海外人気が高まっているということで、生産者を取材してきました。
東南アジア向け輸出 “長崎のイチゴが好評”
県内有数のイチゴの産地・南島原市。

池田 伸輔さんはおよそ2200平方メートルの広さのハウスで長崎県の主力品種「ゆめのか」を育てています。

池田 伸輔さん:
「酸味と甘みが絶妙になって、消費者受けはかなりいい方だと思います」

JA島原雲仙では6年前から県などと協力してイチゴの輸出に乗り出しました。
輸出先は香港がメインで、次いでシンガポール、タイなどとなっていて、輸出量は2020年が55トン2021年が72トンと順調に伸びています。

JA島原雲仙東部基幹営農センター 相川 大志センター長:
「国内販売の中で、時期によって価格が波があって下がる時があるんですが、輸出についてはある程度決めた単価で、安定した単価で販売ができますので、農家の収入、JAとしての販売高の安定につながっていく」
南島原産のイチゴは海外での評価も高く、生産者にとって新たなやりがいにもつながっています。

池田 伸輔さん:
「やはり自分の作ったイチゴが世界でも受けていると考えれば誇らしいなと思いますけど。
自分たちのイチゴがそれだけ認められているというのを誇りに、またさらに励みになりますね」
韓国の刺身のニーズ↑で “活きブリ”が人気
【平】一方、水産物の輸出についても、県によりますと2021年度の輸出額がおよそ42億円と過去最高を更新しています。
中でも輸出が急増しているのが「ブリ」なんです。
長崎県産のブリの輸出に関して先週、長崎税関が一つの調査結果を発表しました。

長崎税関によりますと、去年1年間の長崎県における活魚の輸出額は18億7,000万円で、統計が残る1988年以降で最高となりました。

その内訳は9割以上がブリで、輸出額は17億6,400万円に上り、国内シェアの49%を占めています。
輸出先は全て“韓国”となっていて、税関によりますと、韓国では さばきたての新鮮な刺身を好んで食べる習慣があることから、地理的に近い長崎県産の『活きたブリ』の需要が高まっているということです。
長崎税関では『活きたブリ』の輸出は今後も高い水準で推移していくとみていて、長崎の水産業をけん引する新たな柱となることが期待されています。
一過性にしないために── 西の端の“地の利”をいかす
人口の減少で国内の市場が頭打ちとなる中、輸出への期待は今後ますます大きくなることが予想されます。
ただし、直近の輸出額の伸びは、海外におけるコロナ禍からの外食需要の回復や円安が主な要因ということですから、今後はこの勢いを一過性にしないための取り組みが求められると思います。
長崎の農林水産物や食品のポテンシャルは高いですから、十分に輸出を伸ばせる素地はあると思います。
【住】長崎県の農林水産品や食品の輸出を伸ばしていくために必要なことはなんででょうか。
【平】日本の食材の『質』については、世界で高い評価を得ています。
それは長崎県産のものも同じだと思います。
そうした中で重要なのは「その食材が誰によってどう作られたか」です。

SDGsに対する意識は年々高まっていますが、その中でも、これらの3つは大きく意識されると思います。
・12 つくる責任 つかう責任
・14 海の豊かさを守ろう
・15 陸の豊かさも守ろう
つまり『環境に負荷をかけて供給されていないもの』『持続的に供給することが可能』であることが選ばれるためには必要です。
次に、日本の西の端であるという“地の利”をどう活かすかです。

これには、空路や海路といった『輸出しやすい 輸送手段の拡充』も欠かせないと思います。
さらには「良いものを供給すれば売れる」という「プロダクトアウト」の観点だけでなく、輸出先の国や地域の食の特性などを研究し、ニーズに合った品質や規格などのものを供給する「マーケットイン」の発想が大切だと思います。
いずれにしても、こうしたことは官民が一体となって取り組まないとなかなか難しいですから、そうした取り組みが長崎において進んでいくことに期待したいと思います。