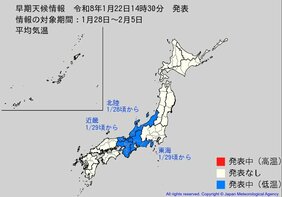岩手県大槌町が10月、今年8月の町の催しで「震災語り部が使った表現に、誤解を招きかねない内容があった」と公表しました。震災伝承の場で何が起きたのか。あの出来事を語り伝えることの、難しさと課題を考えます。
今年8月、お盆で多くの人がふるさとに帰省するのに合わせて、東日本大震災の教訓を伝えようという催しが岩手県大槌町で開かれました。
これに合わせて、津波で多くの職員が犠牲となった旧町役場庁舎の跡地では、町主催の「震災の語り部」のイベントも行われました。

「私は震災の当時、ここで被災したわけではございません」
語り部を務めたのは、町の地域おこし協力隊員の北浦知幸さんです。京都市出身の北浦さんは釜石市の震災応援職員を経て、務めていた関西地方の自治体職員を辞め、現在は大槌町で震災の伝承に関わる調査活動などを行っています。
北浦さんはイベントで、震災当時の防潮堤の高さ6.4メートルが最初に津波警報が出たときの予想の高さ3メートルより高かったことを挙げ、当時の避難について次のように話しました。
(北浦知幸さん)
「一住民として津波が3mきますという時に逃げますか?」
(参加者)
「防災無線とか鳴っていなかったら大丈夫かなと」
(北浦さん)
「鳴っていたら?」
(参加者)
「鳴ってたらやばいかもって」
(北浦さん)
「絶対にどんな場合でも逃げられるかというと・・・前にこういうこと(津波)があったからといって簡単に(避難)できるわけでもないっていうのが、これが現状を示しているんじゃないかなと思います」
この話の内容が「すぐに避難しなくても良いと誤解されかねない」と指摘を受けました。