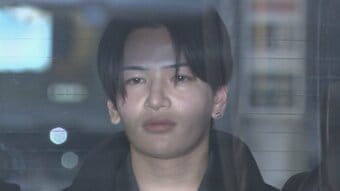4つ目のポイント:子どもは自ら回復する力があることを理解し、見守る
『災害時の子どもの心のケア』では、子どもが気になる行動を一時的にしても、まずは見守ることが大切としています。
「災害を経験したり、被災地の映像を繰り返し見た子どもたちには、次のような様子が見られます。
・いつもよりも元気がない
・イライラしたり、興奮しやすくなる
・日頃していた好きなことをしなくなる
・災害の事ばかり気にしている
・怖い夢を見る
・眠れない
・ご飯やおやつを食べない
・頭が痛い、おなかが痛いなどの体の不調が現れる
・保育園や幼稚園、学校に行きたがらない
・お母さんやお父さんから離れたがらず、甘えん坊になる
『病気になるのでは?』『治療が必要?』と不安になりますが、子どもが一時的にこうした行動や様子を示すことは、いたって自然で正常なことです」
「こうした行動や様子を一時的に示すことで、子どもは、自分を守ってくれる大事なおとなとの信頼関係や、自分の生活の安定を確認します」
「子どもが地震や避難の絵を描いたり、人や町が被災した場面の「ごっこ遊び」も、遊びを使って気持ちを整理したり表現したりするために必要なこと。子どもが自ら回復しようとしている過程なのです。やめさせたりせず、見守りましょう」
普段から身近にいる大人だからこそ子どものためにできることは多くありそうです。一方で、専門機関の受診につなげる必要があるケースもあります。子どもの様子を見ながら、学校や専門機関などとの緊密な連携も求められそうです。
※1:文部科学省 平成24年度 「非常災害時の子どもの心のケアに関する調査報告書」
※2:日本ユニセフ協会 「災害時の子どもの心のケア 一番身近なおとなにしか出来ないこと」