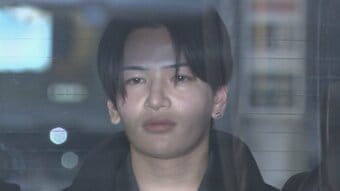2つ目のポイント:「日常」を取り戻すことを助ける

可能な限り『普段の習慣』を保つことも大切であると『災害時の子どもの心のケア』では記されています。
「食事、歯磨き、着替え、睡眠時間を普段通りに保つことは、子どもたちを安心させる手助けになります。
『遊び』は子どもたちの大切な『日常』です。家、避難所、テント、体育館、教室、広場など、「安全」が確保できれば、どんな場所でも結構です。おもちゃや遊び道具として使えるものを用意し、子どもたちが苦しい状況を忘れられるよう、子どもたちの相手をしてください」
「手遊び歌や指相撲など、道具を使わない何気ない遊びや自然とスキンシップが取れる遊びも楽しさや安らぎにつながります」
3つ目のポイント:被災地の映像を繰り返し見せない

“ケアが必要なのは、被災地にいる子どもだけではない”とも『災害時の子どもの心のケア』では指摘しています。被災地の状況がテレビで繰り返し、そして長時間にわたって伝えられた2011年3月の東日本大震災では、多くの専門家が画面を通じて子どもたちが受ける影響を指摘しているとし、注意を呼びかけています。
「乳幼児は、おとなのように言葉での理解ができないので、映像や画像が伝える事実を十分に把握できません。おとな以上に映像や画像から大きな衝撃を受ける可能性があります。
時間の感覚がまだ発達していない子は、過去の出来事を録画再生したものを『今この瞬間に起きている』と思ってしまいます」
「ニュースやインターネットの情報を自発的に得ることができる子どもたち(小学校3〜4年生より上の年齢)も、感受性が豊かであるために、被災地の映像に触れる時間があまり増えると、コントロールできない程、感情移入をしてしまう恐れがあります」
「日ごろよく観ていたテレビ番組やお気に入りのDVDなどがあったら、できるだけそうしたものを観せてください」