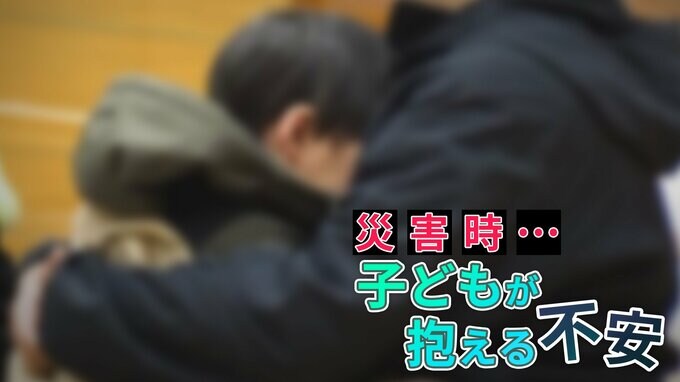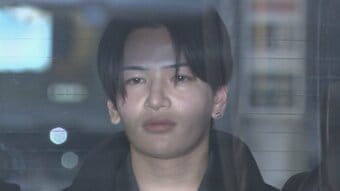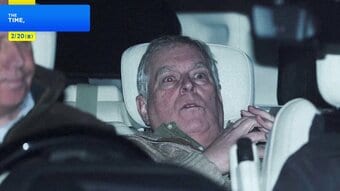石川県で最大震度7を観測した能登半島地震。日常が奪われ、大人でも極めて困難な状況ですが、子どもは「助けて」と言わなくても、普段通りに過ごしているように見えても、大きなストレスを受けていることがあるといいます。身近な大人たちが子どもの心のダメージを最小限に抑えるためにできることとは。
被災が子どもにもたらす心の健康問題 過去には年齢が低いほど増す傾向も

文部科学省の調査(※1)によると、東日本大震災では、PTSDが疑われる症状が1つでも見られる子どもは、岩手県では11.3%、宮城県では19.0%、福島県で22.9%にのぼりました。
被害の大きい地域ほど、年齢が低くなるほど、また障害等がある場合に、PTSD の可能性がある子どもの割合が増す傾向が見られたといいます。
2024年の元日に発生した能登半島地震からまもなく1週間を迎えようとしています。子どもたちの心のケアのために、身近にいる大人たちができることはあるのでしょうか。
日本ユニセフ協会は、「災害時の子どもの心のケア(※2)」をまとめて、子どもの心に落ち着きを与え、トラウマの傷口を最小限にするため、普段から一番身近にいる人だからこそできることを発信をしています。ポイントは大きく4つあるといいます。
1つ目のポイント:「安心感」を与える
安らぎは心のケアの第一歩で、子どもの回復力を左右すると『災害時の子どもの心のケア』では記されています。では、具体的にどのように安らぎを与えればいいのでしょうか。
「子どもたちに寄り添ってください。いつもよりも少し意識して、親や周りのおとなが一緒にいる時間やスキンシップを増やしてください。可能なら、家族で一緒に楽しく遊ぶ時間を持ってください。
子どもの不安を笑ったりせず、子どもたちの言うことに耳を傾け、疑問や心配に思うことには、安心感を与えながら、簡単な言葉で、穏やかに、そして正直に答えてください」
「子どもが、心に抱く恐怖を言葉にすること、そして、それを誰かがちゃんと聞くことは、子どもたちの質問に答えることと同じくらい重要なことです」
「まだ言葉を発していなかったり、言葉によるコミュニケーションができない子どもたちにも、同じように声をかけてください。みなさんの表情や仕草が、子どもたちに安心感を与えます」
「子どもたちを安心させられるようなことなら、どんなことでもやってみてください。子どもの隣に座って、ふたりだけの静かな時間を過ごす事でも助けになるかもしれません」