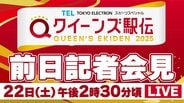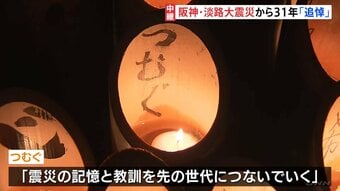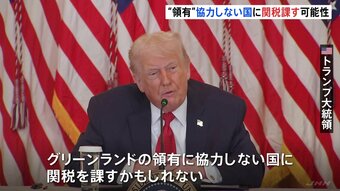ニューイヤー駅伝は2区か、3区か?
――ニューイヤー駅伝は3回出場して21年は5区区間3位、22年は6区区間6位、23年が5区区間2位でした。
塩尻:
6区を走ったときはチームの位置が(14位と)後方だったので、(オーバーペース気味に入るなど)自分の走りも焦りがありました。5区の2回は区間3位と区間2位で、走り自体は悪くありませんでしたが、後半5kmでリズムを少し落としてしまい、結果として区間賞を取れませんでした。10km前後の大きな橋を渡るときだけ風向きが変わるのですが、上手く呼吸が入ってこないというか…リズムが崩れてしまって上手く走れませんでした。今年はどの区間になっても最後までしっかりリズムを刻んで走れば、区間賞も十分狙えるかな、と思っています。
――今回から2区が21.9kmと最長区間になり、3区も少し長くなって15.4kmに。高橋健一監督は2区起用の可能性を言及していますが、塩尻選手自身は3区の方がリズム良く走れそうだと、東日本実業団駅伝後にコメントしていました。
塩尻:
そうですね。合わせやすいのは3区の方だと思っています。駅伝はチーム事情も区間配置に反映されるので、まだ出場区間は聞いていませんが、走るとなれば(2区でも)その区間で全力を尽くします。
――箱根駅伝は2区(23.1km)で、日本人区間歴代最高タイム(当時)で走りました。22~23kmの距離は問題ないと思われますが?
塩尻:
箱根駅伝はどの区間も20km以上の距離があるので、学生の頃は年間を通して20km以上の距離を走る練習に取り組んでいます。実業団選手にもハーフマラソンや、もっと長いマラソンに取り組む選手もいるのですが、全員が20km以上を走るわけではありません。年間での練習計画が学生とは違ってきます。
――新しい区間距離になって、3区にエースや一番調子の良い選手を起用する、と話す指導者も多いと感じています。3区は、日本選手権と同じようなハイレベルの激戦になるかもしれません。
塩尻:
誰が集まるかは、あまり意識しないようにしています。区間賞は目標にしているので、区間エントリーが(12月30日に)決まり、速い選手が多いと大変だなと思いますが、チーム全体の戦いを一番に考えます。決められた区間でチームに貢献することですね。周りのチームを想定してではなく、自分のチームでどこに入るのが一番良いか。それが大事かな、と思っています。
パリ五輪へのスケジュール
――日本選手権の結果で世界ランキングのポイントも上昇し、Road to Paris 2024(標準記録突破者と世界ランキング上位者を1国3人でカウントした世界陸連作成のリスト)の順位が17位(10000mの出場選手枠は27人)に上がりました。来年の出場レースはどうなりそうですか。
塩尻:
ニューイヤー駅伝のあとは全国都道府県対抗男子駅伝(1月21日)に出場することが決まっています。トラックは5月3日の日本選手権10000mが決まっているくらいで、それ以外はまだ予定を詰められていません。記録とポイントを取るために、どこかでもう1レース狙えないかと、監督やコーチと話しています。海外も含めてポイントの高い大会を検討している段階です。
――どういったトレーニングで強化していく予定ですか。
塩尻:
トレーニングで言えば結局、より速いスピードで、より長い距離を、というところが求められます。ニューイヤー駅伝が終わってから3月、4月まででどちらも、総合的にトレーニングを組み立てていければ、と考えています。今年の夏は国際大会が続き(7月にアジア選手権5000m、8月に世界陸上5000m、9月にアジア大会10000m)、例年に比べて練習の積み上げが、強化の面では十分にできていませんでした。しっかりトレーニングを積んで、来シーズンの試合に臨めればいいかな、と思っています。
――富士通は東日本実業団駅伝では4連勝中ですが、ニューイヤー駅伝では21年に優勝した後、22年は12位、23年は2位と勝っていません。
塩尻:
東日本とニューイヤーでは同じ7区間でも、全体の距離が20kmくらい変わります(東日本76.9km、ニューイヤー駅伝100km)。東日本ではチームの(トラックの日本代表選手が多い)強みが出ているのに対し、ニューイヤーではライバルチームの強みが出ています。だからといってニューイヤーで勝てないとは、チームの誰ひとりとして思っていません。国内でも強い選手が集まっているのが富士通です。3年前に優勝しましたし、ニューイヤー駅伝に合わせていけば、必ず優勝できます。メンバーがどれだけベストなパフォーマンスを発揮できるか。その一員として、元旦当日に良い走りができればいいな、と思っています。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)