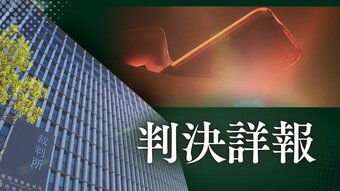◆ガザ地区で「今起きていること」
いろいろな議論がありますが、大前提として「今起こっている状況」が提示されました。
● 住民の65%が国内避難民
● 少なくとも地区の45%の住居が破壊または損壊
● 敵対行為前に比べて水の消費量が92%減少
● 基本的な食料品の現在の市場在庫は1~23日分、通常のパンの半分の量を受け取るのに必要な時間は平均4~6時間
● 62万5000人の生徒が教育を受けられず、51%以上の教育機関が被災
このような状況が共有されました。声明を出すことも含めて、「意味はない」と考えるかどうか。「心を寄せる」ために、世界中でデモが起きている。国際人権法に携わっている研究者は、戦争犯罪との国際司法裁判所の認定があってしか議論ができないのか。そうした切実な議論が、「緊急ラウンドテーブル」でされました。
西南学院大学法学部の根岸陽太准教授:今回は、何かを決めようという会議というよりは、皆様の意識形成、学会として少なくともこれを話し合う機会を持ち、個々に持ち帰っていただく、有志で集まっていただく、さらに学会として何か動いていくことができるか、ということに向けての話し合いでしたので、何か結論を申し上げるわけではありません。
実体的な本質的なところとしては、例えば「10月7日(ハマスによるイスラエル急襲)以前を扱うのか」、それとも「以後だけを見てみる」のか。
個別の論点に関しても、(国際司法裁判所の)裁判を待つべきなのか。またはそもそも事実調査もまだ関し確定的な意見がないのだから、「違反している可能性がある」「ジェノサイドが起こる可能性がある」と伝えていくべきなのか。
また、学会として一致するべきなのか、特定できる部分に集中していくのか。それとも総合的に難しいのであれば、例えば有志で深掘りしていくとか、論点整理だけでも専門的な貢献になりうる。学会として来年以降の企画でも扱っていくことができる、ということも十分に話されました。
これだけでも、皆さんがこんなに、朝早くから集まっていただいたことの成果だと思います。ひとまずこの選択肢を有志で取り集め、それを文字化して皆様にお届けしますので、見ていただいた中で各自、各グループ、そして学会のアクションにつなげていただければと思います。
できることはささやかかもしれませんが、今起きている状況、そこで暮らしている子供たちに心を寄せていこう。考えること、思うこと、声明を出すこと、デモをすること。いろいろなやり方があると思うし、自分がやれないにしても、やっている人たちに「自分の代わりにもしてもらっているのかな」とちょっとした応援をしてみる。街中で見かけたら手を振ってみるでもいい。
「戦争を止めることができるか」と冷笑されますが、それはできないです。でも子供たちの命が失われているのを見て、冷笑できるのでしょうか。動いている人たちを笑うことに、あなたの心がそのまま映っている。そうではなくて、やっている人に「ありがとう」と、少しでも心を寄せていきたい。そんなことを考えた、研究者の話し合いでした。たった45分でしたが、非常に熱がこもっていました。
◆神戸金史(かんべ・かねぶみ)
1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件や関東大震災時の朝鮮人虐殺などを取材して、ラジオドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』を制作した。近著に、その取材過程を詳述した『ドキュメンタリーの現在 九州で足もとを掘る』(共著、石風社)。