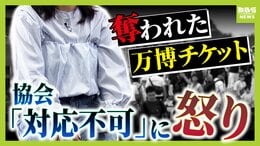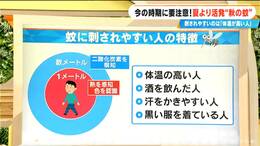最先端の街づくりをしてきた渋谷だからこそ
若新雄純 慶応大学特任准教授:
でも今回の件はいろいろ残念だなと思います。渋谷区どうしちゃったのかなって感じです。ネットでも話題になっていますが、もともと「渋谷を盛り上げてくれ」って訴えておきながら、盛り上がりすぎて、人が集まりすぎたので今度は「来ないで」というのは…。
この言い方は群衆に対するメッセージなんですよね。まず群衆は「皆さん」じゃないですか。「皆さん来ないで」と言われても誰も「自分のこと」だとは思わない。自分が行ったって他の人がいなければ人数減るとか。例えば「外国人の方はぜひこういうところの方が言語案内がサポートされてますよ」とか、具体的な人に対してこうしてくださいと言えば変わると思う。
熱が盛り上がった一方で「お客さんを集めたい」つまりにぎわいを作りたい地域は、別に地方に行かなくても、都内にもたくさんある。せっかく盛り上がったものを、直線的に止めるんじゃなくて、渋谷を中心に、例えばこういう人は「赤羽で」とか、こういう人は「蒲田で」とか、路上でも飲みたいって人は「路上でも飲める地域はここですよ」と。
具体的に呼びかけて分散させて「東京全体で盛り上げましょう」みたいな方が、よりトラブルも減り、熱が渋谷を中心に上がったと思う。そういうことはやれたはず。
井上貴博キャスター:
渋谷区長は苦渋の決断だったと思います。しかし「自粛を促す」というのはコロナ禍に近い感覚で、あまり公の機関が言うのは好きじゃないなと感じた。
渋谷区は2023年の1年間でハロウィーン対策費に5000万円ぐらい予算を付けている。「来ないでくれ」とするなら、その5000万円を「イベントにしますと、入場料を取ります」という形があったんじゃないかなと思いました。
若新雄純 慶応大学特任准教授:
まさに新型コロナのときも最初は「自粛」でしたけど、途中からは「分散」を呼びかけたし、距離を取ることを訴えた。そうやってバラバラにしたり、密度を下げたりすれば、実は全体的に参加する人は増えるけれど、困難が減るという可能性もあると思う。
そこはやっぱり、いろんな最先端の街づくりをしてきた渋谷だからこそ、もう一歩工夫できたのかなという気はする。
それぞれ連携は直接していないようですが、今回も他の街と含めて原宿・池袋などと分散してやったら、本当はスタンプラリーだったり、時間差でいろんなことを企画することができただろうなと思います。