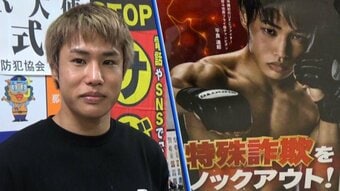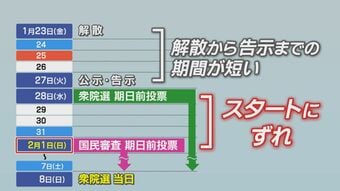壺屋焼きの種類は2つ その違いは
壺屋焼の種類は主に2つ。南部の土を素材にザラザラとした質感が特徴の「荒焼(アラヤチ)」と、北部の土を使って光沢感や模様を付けた「上焼(ジョーヤチ)」。
中でも大きな違いは「釉薬(ゆうやく)」の有無です。
比嘉立広 学芸員
「釉薬というのは自然の鉱物や植物の灰などを混ぜて作るものなんですが、この液体をかけて焼くと、釉薬は高温で焼いて溶けるとガラス質に変わる特徴があって、釉薬を使うことで、上焼はカラフルな焼き物として仕上がっています」

壺屋焼が栄えた1680年代は荒焼が主流でしたが、戦後食器として焼き物が使われ始めたことから上焼の需要が高まり、今では生産量のほとんどを占めています。
壺屋には琉球王国時代から使われていた登窯が今も残っていてその代表が「東ヌ窯(アガリヌカマ)」と「南ヌ窯(フェーヌカマ)」です。国の重要文化財に指定されています。