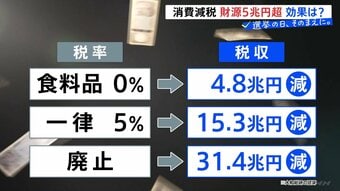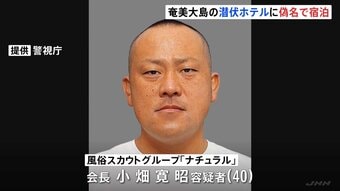なぜデマは拡散したのか

「不逞鮮人一千名と横浜で戦闘開始」
「不逞鮮人各所に放火」
震災直後の新聞各紙の見出しです。デマに基づいた偽りの記事です。
繰り返される“不逞鮮人”という言葉。“不逞”とは不平を抱き、従順で無いこと。“鮮人”には侮蔑的なニュアンスが込められています。
テレビはもちろんラジオも無い時代。情報源としての新聞の存在は、今とは比べものにならないほど大きいものでした。
朝鮮人に対する怒りと不安をあおるようなデマを、なぜ新聞はそのまま伝えたのか。鍵を握る文書が、防衛省に保管されていました。
震災時の至急電文が綴られています。
震災時の至急電文より
「朝鮮人は各地に放火し、不逞の目的を遂行せんとし、現に東京市内に於いて爆弾を所持し、石油を注ぎて放火するものあり。鮮人の行動に対しては厳密なる取り締まりを加えられたし」
発信者は内務省警保局長。いまで言えば警察庁長官にあたります。この電文は東京近郊で被害を免れた海軍の送信所から全国に発せられました。
送信所の跡地にはモニュメントが残されています。平形さんに案内してもらいました。

平形千恵子さん
「関東大震災の時、救援電波を出して、多くの人を助けたとあるんですね。ここが『不逞鮮人をちゃんと調べろ、取り締まれ』と出した大元なんです。それだけは書かない」
東京の新聞社が壊滅的な被害を受け、震災報道は地方の新聞が担うことになりました。
不逞朝鮮人の噂は耳にするものの、現場に入れず裏付けがとれない。こうした中、内務省の電文を傍受した記者たちはこう確信します。
「やはり朝鮮人暴動は事実だった」
ジャーナリストの渡辺延志さん。関東大震災におけるデマが虐殺にまで発展した背景を歴史的に読み解く必要があると言います。

ジャーナリスト 渡辺延志さん
「日本は1910年に韓国を併合するわけですけど、日本の支配に抵抗する義兵闘争というのがあるんですが、ここでも1万数千人の武装した朝鮮人が殺された。その後は例えば三・一運動がありますし、私が考えるのは1918年に始まるシベリア出兵ですよね」
朝鮮を支配しようとする日本と、これに抵抗する朝鮮の人々。
古くは日清戦争から震災間際のシベリア出兵まで、抵抗と弾圧が繰り返される中で、日本社会には「不逞鮮人」のイメージが根付いてゆきます。
デマは簡単に信じられ、怒り狂った民衆を前に当局の対応は一貫せず、新聞社は誤報を訂正する機会を逸しました。不逞鮮人の記事は100年たった現在、虐殺否定論の根拠として利用されています。
渡辺延志さん
「読者に何かを伝えようとして、結果として実は誤報だったと。しかし、その誤報をただす機会がなかったという事だと思うんです。その誤報も忘れられて、もっともっと大きな誤報というものを、戦争を繰り返すうちに重ねてしまった」
本庄市の虐殺事件について取材する中で、こんな記事を目にしました。
「新聞記者・馬場安吉氏は極力、善良朝鮮人の保護を説き、流言飛語に惑わされぬよう説き、町内をも遊説し」
デマに振り回された記者ばかりではなかったのです。
人々を説得しようと飛び回ったのは、当時の群馬新聞・本庄支局長の馬場安吉。ただ、興奮した市民の耳に馬場の訴えは届きませんでした。
その慰霊碑は本庄市の倉庫に保管されていました。

震災から1年後の1924年、馬場安吉が本庄の記者仲間に呼びかけて作った朝鮮人犠牲者の慰霊碑です。
戦後「鮮人」の文字が差別にあたるとして立て替えられ、この慰霊碑の所在は長いこと忘れられていました。
38年前、群馬県内でこの碑を探し当てた嶋田道雄さんは碑に込められた思いをこう語ります。

嶋田道雄さん
「群衆の前に立って、やめろと立ちはだかったけど止められずに、本庄で80何人が亡くなってますから、思いは強かったと」
新聞のデマ情報が結果的に虐殺を招いてしまった事に対する新聞人・馬場安吉の無念、自責の念はいかばかりだったのでしょうか。