◆たまたまこの夏に読んだ2冊の本
この夏に私が買った本を2冊持ってきました。「この国の戦争:太平洋戦争をどう読むか」(河出新書)は、小説家の奥泉光さんと歴史学者の加藤陽子さんの対談で、たいへん読みやすく、どうして日本がこういう戦争を引き起こしていったのかが、専門家の加藤さんと奥泉さんが対談する形で示されています。
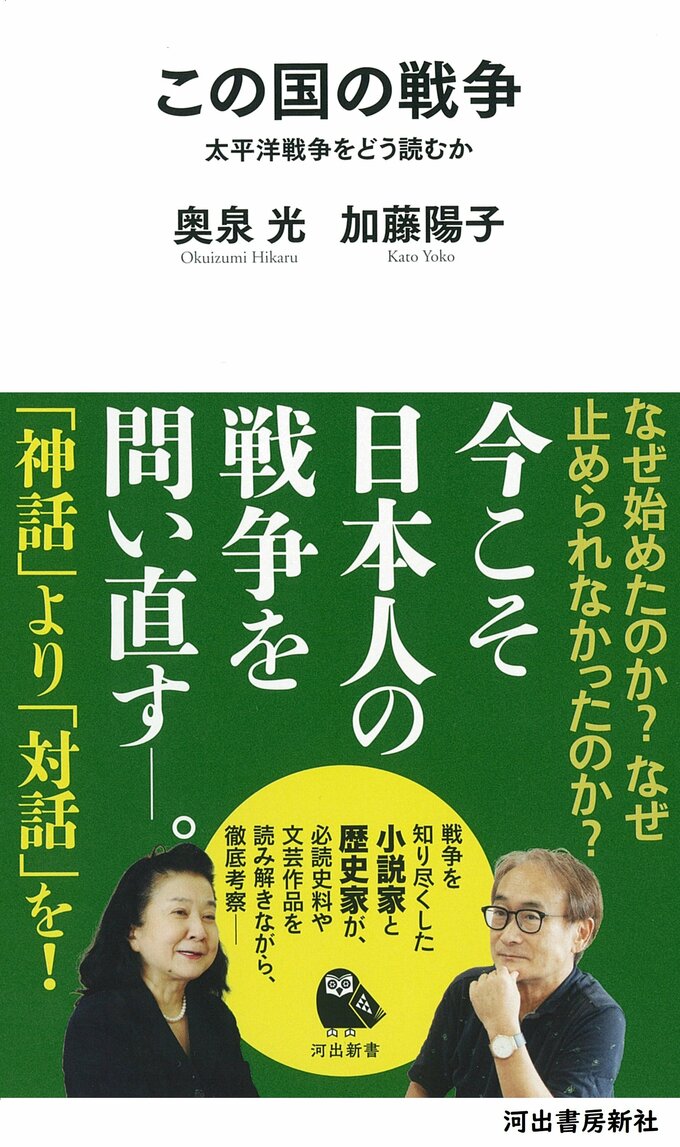
奥泉光・加藤陽子『この国の戦争:太平洋戦争をどう読むか』(河出新書、税込968円)
今こそ、「日本人の戦争」を問い直す。日本はなぜ、あの戦争を始めたのか? なぜ止められなかったのか? 戦争を知り尽くした小説家と歴史家が、日本近代の画期をなした言葉や史料を読み解き、それぞれが必読と推す文芸作品や手記などにも触れつつ、徹底考察。「わかりやすい物語」に抗して交わされ続ける対話。
例えば、日本が受諾するかどうかが最後に焦点になった連合国のポツダム宣言には「日本軍の軍隊が完全に武装解除された後は、それぞれ家庭に復帰して平和的な生活を営む機会を得られる」と書いてあります。
ところが戦争末期の日本国家は、軍部の指示によってこの条項を隠して報道させました。「生きて虜囚の辱めを受けず」という教育をずっとしてきたわけです。加藤さんは「これを正直に書けば、国民の抗戦意識が鈍ると思ったからでしょう。為政者はこのようなことをやります」と書いています(144ページ)。
◆実体とはかけ離れた「数字」
もう1冊は、昔の本ですが、評論家の山本七平さん(1921年~1991年)が書いた「一下級将校の見た帝国陸軍」(文春文庫)です。21歳で徴兵された山本さんが、自分の見た日本軍の状況を書いています。
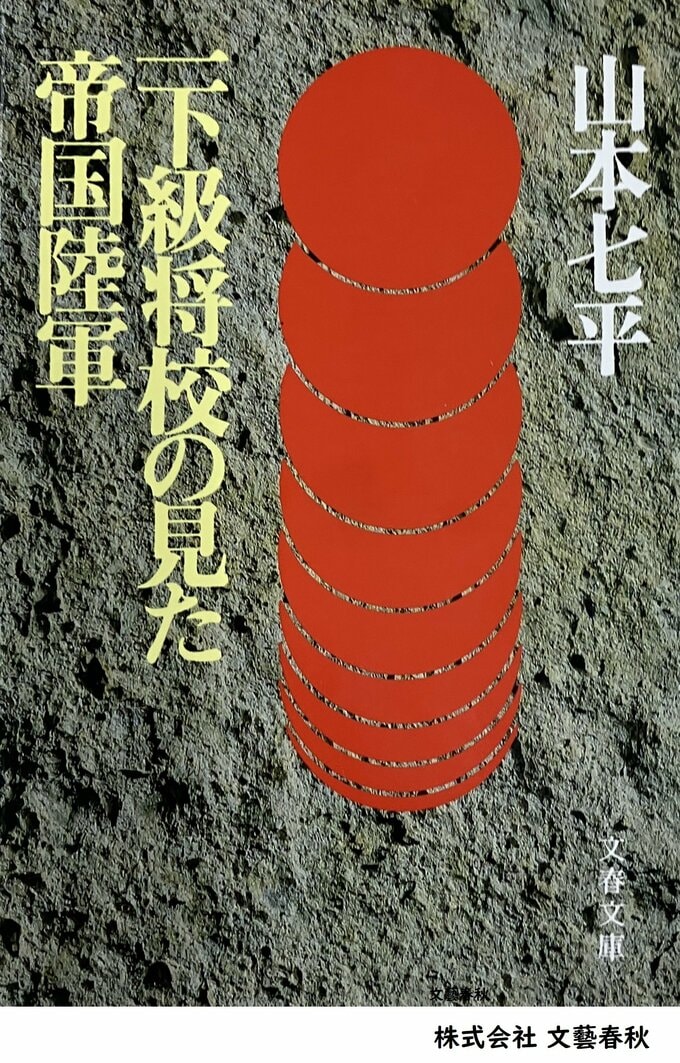
山本七平『一下級将校の見た帝国陸軍』(文春文庫、税込726円)
「帝国陸軍」とは何だったのか。すべてが規則ずくめで大官僚機構ともいえる日本軍隊を、北部ルソンで野砲連隊本部の少尉として惨烈な体験をした著者が、徹底的に分析追求した力作。
山本七平さんと聞くと、私が学生の頃は、中曽根内閣の諮問機関「臨時教育審議会」で委員をしていて、保守系内閣を手伝っている「体制寄りの人」という印象がありました。
ところが、この方が見た帝国陸軍論は、実体験。読んで初めて「員数主義」という言葉を知りました。「員」とは「頭数」の意味です。員数主義がはびこっていた、と徹底的に陸軍の状況を追及していきます。
元来は員数とは、物品の数を意味するだけであって、いわゆる「員数検査」とは、一般社会の棚卸しと少しも変わらず、帳簿上の数と現物の数とが一致しているかどうかを調べるだけのことである。従って、問題は、検査そのものより、検査の内容と意味づけにあった。すなわち「数さえ合えばそれでよい」が基本的態度であって、その内実は全く問わないという形式 主義、それが員数主義の基本なのである 。
それは当然に「員数が合わなければ処罰」から「員数さえ合っていれば不問」へと進む。 従って「員数を合わす」ためには何でもやる。(135~136ページ)
例えば、「上官から暴力を振るわれた奴は手を挙げろ」と聞いても、誰も上げない。だから「いません」と報告を上げていく。数字が整っていればそれでいいとみなしてしまう軍隊の悪しき風習を語っています。














