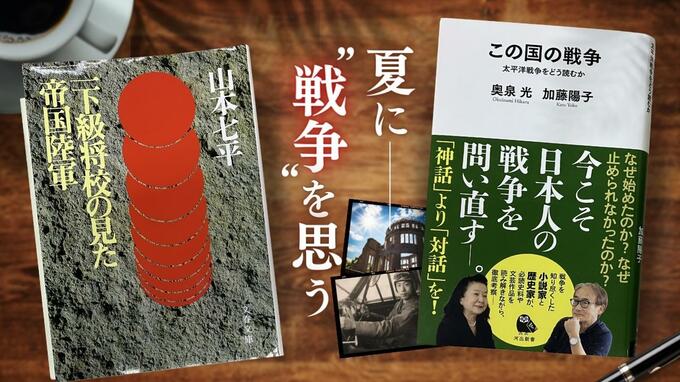広島・長崎の原爆に玉音放送。お盆を迎える8月には、戦争と平和をめぐる報道が増える。大日本帝国は暴走し、1945年に滅亡した。片棒を担いだメディアの責任は消えない。戦争の悲惨な実相から離れた空虚な「分かりやすい物語」が飛び交う中で、RKB毎日放送の神戸金史(かんべ・かねぶみ)解説委員長が8月8日、RKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』でおすすめの書籍を紹介した。
◆“8月ジャーナリズム”と「常夏記者」

8月になると、メディアがいきなり戦争に関する報道を集中的に始めます。“8月ジャーナリズム”という言葉には、半分揶揄するようなニュアンスもあります。8月だけではいけないのは当たり前なのですが、でも「せめて8月だけでもちゃんとやりたい」という気持ちも、“8月ジャーナリズム”の中にはあるんです。
そんな中、8月5日の毎日新聞のコラム「現代をみる」に、「20年近く、戦争にまつわる取材と報道を一年中やっている」と書いた栗原俊雄記者。彼は一年中戦争報道をしているので「常夏記者」と言われているそうです。
◆「尊い犠牲」「英霊」という言葉

栗原記者が書いたコラムは「『英霊』という言葉が隠すこと」という見出しでした。東京大空襲の法要には記事化の予定がなくても参列し、沖縄やサイパン、シベリア、旧満州などで手を合わせて「戦没者を悼む気持ちは人後に落ちないと思っている」という栗原記者ですが、「英霊」とか「尊い犠牲の上に、今、われわれが享受する平和と繁栄があります」といった言葉は使わないようにしています。
「英霊」とか「尊い犠牲」という言葉を使うと、「『誰の』もしくは『どの団体の』どんな判断ミスで出口なき戦争に突き進んだのかという史実が後景に退き、責任が見えにくくなる」というのが、理由の一つ目。
二つ目は、現代の「平和と繁栄」を強調すると、戦後80年近くたっても未解決の戦後補償問題(たとえば民間人空襲被害者)が多数あり、戦争被害が続いていることが伝わらないから。
この2つの理由で、「尊い犠牲」「英霊」という言葉を避けるようにしている、というのです。とてもいい視点だと思いました。