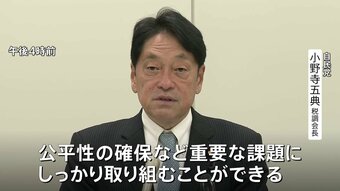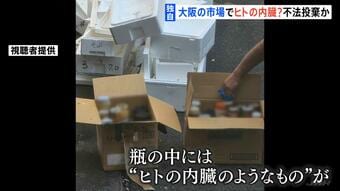夏休みで学校がなくても、子どもには意欲をもって過ごしてほしいと感じる人は多いだろう。そんな時、子どもを応援するつもりが、実は逆効果になっている言葉がある。「頑張って」もその一つだ。専門家は「頑張ってるね」に言い換えてほしいと指摘する。「るね」の2文字がつくだけで一体何が変わるというのか。そこには、子どもの意欲を高める驚きの激励効果があった。
「頑張って」が子どもの意欲を破壊する?!親のよかれに注意
夏休みに入り、子どもが家でダラダラしていて、心配に思っている親もいるだろう。かといって、子どもに「ちゃんとしなさい!」といったところで、子どもがちゃんとするケースはまれだ。一体どうすればいいのか、親は焦るばかりだ。

実は、子どもの行動には親の言動が大きく関わっていると指摘する専門家がいる。犯罪心理学者の出口保行さんは著書『犯罪心理学者が教える 子どもを呪う言葉・救う言葉』のなかで、親がよかれとおもってかけている言葉が、子どもの意欲を破壊しているケースがあると警鐘を鳴らしている。
ーー著書の中では「頑張りなさい」では子どもは頑張れないと指摘されていますね。どういうことなんでしょうか?
「『頑張りなさい』って、親は子どもに対して発破をかけるつもりでよく言いますよね。その言葉をかけるタイミングによっては、子どもの意欲を失わせる可能性があるのです」
ーータイミングですか?
「つまり、子どもの様子をしっかり観察して、適切な言葉がかけられているか、ということです。頑張っていないように見えても、実は子どもは子どもなりに頑張っていることが結構あります。頑張っていて、苦しみながら進んでいるわけです。そこを理解せずに、いきなり親から『頑張りなさい』とか『頑張って』と言われると、こんなに頑張ってるのにと、意欲をそがれてしまうんです」
ーー怠けているように見えても、本人はやらなきゃな、頑張ろうと感じていることもあるかもしれませんね…。
「そういうタイミングで『頑張って』なんて言葉が降ってきたら、子どもは、こんだけ頑張ってるのにまだやれっていうのかよって、その後は頑張るのをやめちゃうんですよね」
子どもがどのような状況にあるのかを見定めた上で、子どもに対する声かけをすることが重要だと出口さんは話す。タイミングを間違えた「頑張りなさい」「頑張って」は、親が子どもの気持ちを考えず、結果的に意欲を失わせてしまう典型的な例だという。
では、子どもの意欲を高める声かけとはどんなものなのだろうか?