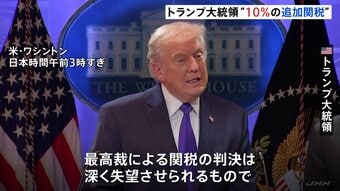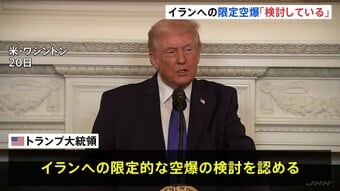岸田総理は、7月16日から19日まで、総理就任後初めて、中東3か国=サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、カタールを歴訪した。いずれも日本にとっては重要な石油、液化天然ガス(LNG)の調達先だ。資源エネルギー外交、また、安全保障面での連携強化を図る訪問だったが、同行取材で見えた成果と課題を考える。
脱炭素化、気候変動対策…どこまで本気?
寒い。とにかく寒い。これが最初の訪問国サウジアラビアに着いた私の第一印象だ。UAE、カタールも共通するが、どこもかしこも建物内がキンキンに冷えているのである。エアコンの設定温度を見ると20度、又はそれ以下だ。外国から来た客人へのもてなしという面もあったのかも知れないが、節電に励む霞が関の標準的な設定温度28度に慣れた身にはこたえる。外に出れば灼熱、中に入れば急冷。まるでサウナと水風呂を繰り返しているようだが、ちっともサウナのように整わない。整うどころか、自律神経がどうにかなりそうだ。
日中、外気温は40度を超え、暴力的な日差しで日なたには5分といられない。それでも外にいる人をぽつりぽつりと見かける。路上でゴミ掃除をする清掃員、建設現場で働く作業員などだ。額に汗して働く彼らの殆どは外国人出稼ぎ労働者と見受けられる。莫大なオイルマネーの力に改めて思いを馳せる。
ここで素朴な疑問が湧いてくる。これだけ国中の建物をガンガン冷やせば、当然、大量の電力を消費する。中東諸国は、化石燃料依存からの脱却=“脱炭素化”を模索してはいるが、まだ電力の供給源は化石燃料(石油、天然ガス)に頼っている。気候変動対策にも力を入れるというが、一体、“エコ”にどこまで本気なのだろうか。今回の総理訪問の目的の一つに、脱炭素化、気候変動対策で日本の先端技術を売り込む、という点もあったはずだが…。
その疑問を、中東情勢に詳しいある専門家にぶつけてみた。解説は実に明快だった。
「サウジやUAE、カタールが脱炭素や気候変動対策をやるのは、欧米から人権だなんだと騒がれないため。そして、脱炭素がビジネスになるのを分かっているから。サウジアラビアは図体が大きすぎて脱炭素は難しい。UAEは関心は高いが、気候変動対策に取り組むことで、人権をはじめ国が抱える問題からうまいこと目を背けたい。カタールは小さすぎて、脱炭素に実はそれほど関心はない」
3か国それぞれ事情も思惑も異なり、いわば“同床異夢”というわけだ。