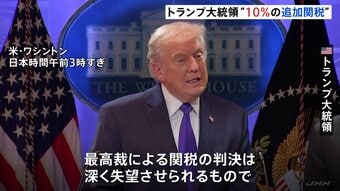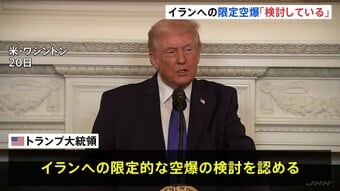中東の“空白”を埋めるもの

一方で、政治的な課題は重い。
日本の総理によるサウジアラビア、UAE訪問は、3年あまり空いた(カタールは10年ぶり)。その間に、中東をめぐる国際社会の構図は大きく変わった。ある外務省幹部は、今回の訪問について「これ以上、遅れさせられなかった」と語った。意識しているのは、中国の存在だ。中東情勢に詳しい専門家はこう解説する。
「中東ではアメリカの存在感が低下している。米軍はそのまま残っているし、引いているわけではないが、“影が薄くなっている”と受け止められている。そこに中国が次第に進出した。そして、中東の国々は、日本や欧米のように中国を“脅威”だなんて、これっぽっちも思っていない」
実際、中国は今年3月、サウジアラビアをイランの国交正常化という難易度の高い政治課題をやってのけ、世界をあっと言わせた。中国なしでは合意できなかったのか、合意は今後守られるのかといった問いは別として、「私が仲介しました」と発表できる役割をしたのは紛れもない事実だ。
今回の総理訪問で、日本としては対中国、対ロシアを念頭に「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序」の重要性を、直接訴える狙いがあった。物事がトップダウンで決まるとされる中東諸国において、首脳同士、腹を割って対話をすることは必要不可欠だった。
ただ、総理の訴えがどこまで響いたかはまだ見通せない。中東諸国において、「法の支配」、「自由」、「民主主義」などの価値観は、日本の捉え方とは異なる。
今回訪問した3か国とは、外交・防衛分野で対話の機会を増やすことで合意した。湾岸協力会議(GCC)と外相レベルでの対話を定例化することでも一致した。中東訪問を主導した政府関係者は語る。「中国側か、こちら(日米欧)側か、と“踏み絵”を迫るような形ではなく、日本の国益にかなう協力、パートナシップを模索する」。日本ならではのやり方、その真価が問われるのはこれからだ。
TBSテレビ政治部 外務省担当キャップ 宮本晴代