“安全装置”が準備不足だった?
「マイナンバー制度WG」メンバー 武蔵大学 庄司教授:
自動車に例えてみますが、アクセルを踏んでいくと同時にブレーキやエアバッグ、自動車保険などの“安全装置”というのをしっかり準備していく必要があるなというふうに思います。
山本キャスター:
“安全装置”という言葉がありましたが、このトラブルが続いている理由について、庄司さんは『安全装置の準備不足』があると。
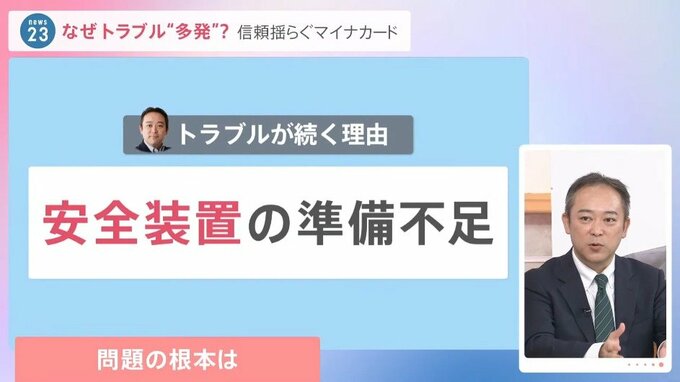
「マイナンバー制度WG」メンバー 武蔵大学 庄司教授:
いわゆる『ヒヤリハット』とも言いますが、実際にトラブルになっていないものも含めて、「こういうミスがあった」「エラーが起きそうだ」など、そういった情報をいち早く集めて分析して、今のシステムを改修していくというような仕組みが普段から機能していれば、こういった件数というのは抑えられたと思います。
それから被害が起きても、最小限に抑えられるように自分でもデータを確認できる仕組みを使ってもらうようにするなど、自治体がしっかり手順通りやっているかどうか確認していく仕組みを用意しておく。そういったことを“安全措置”というふうに呼んでいます。それがまだ準備しきれていなかったのだと思います。
小川キャスター:
でも満を持してのマイナンバー制度、マイナンバーカードだったわけですよね。なぜ準備不足というのがここまで起きてしまったのでしょうか?
「マイナンバー制度WG」メンバー 武蔵大学 庄司教授:
確かにこういった仕組みが必要だということは、もう長年ずっと言われてきたことであるわけですけれども、コロナ対応の中で行政がオンラインでサービスを受けられるようにしていく必要があった。そのためには本人確認のツールが必要だということで、コロナで急いだという部分はあったと思います。
小川キャスター:
拙速だったというところもあるんでしょうか?
データサイエンティスト 宮田氏:
今おっしゃっていたポイントもすごく大事ですし、もう一つはマイナンバーカードを登録し、発行するという仕組み作りをずっとしていたんですが、これをカードを使うっていうところですよね。今回のように保険証と紐付けるなど、これからいろいろなデータと紐付けながら使っていくというようなデザインが十分できていなかったので、つまり登録の中では露見しづらかった問題が、今明らかになってきている。ここから先は、いかにマイナンバーカードというのを、社会の中で運用していくかということを踏まえた上で、いろいろな仕組みを各自治体も作っていく必要があるんじゃないかなと思います。
山本キャスター:
宮田さんはトラブルが続く根本の理由として、『グランドデザインがない中での付け焼刃のIT実装』だと。
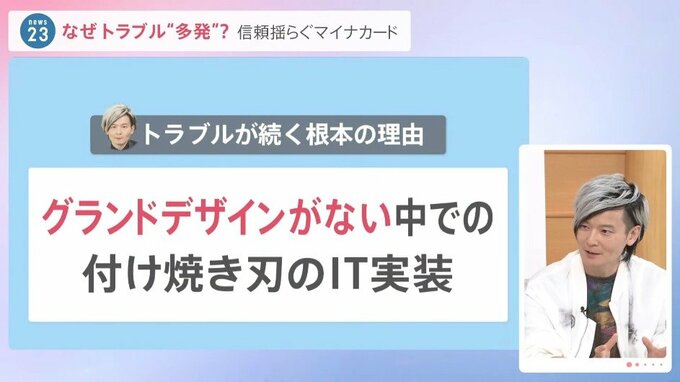
データサイエンティスト 宮田氏:
時の大臣の施策の問題によって、この問題が起こっているわけではないですよね。日本がこれまで政府や、行政で積み上げてきた様々なエラーを今明らかにしてるだけなんですよね。これがなぜ起こってきているかというと、つまりマイナンバーという仕組みは、様々な場面で使うために本来作られているんですが、登録の部分というところに注力しすぎてしまっていると。
例えばそれを作る行政側も、大抵1年~2年の任期の中で問題が起こらないようにしていくということになります。さらに言えば業者は利益重視ということではないんですけど、任期の中で「登録」の部分というところをまず一生懸命作ると。「引き出して使う」というところは、「登録」のスパンの中ではチェックされにくいことがあったので、まさに今「使う」というフェーズによってこういう問題が起こってきている。まさに今、河野大臣は長年引き継がれてきたこの“負の遺産”を整理しているということなので、この整理そのものを問題視するのではなく、確実に遅かれ早かれ出てきた問題なので、その上で、どういう仕組みを作っていくのかということが今必要なことだと思います。














