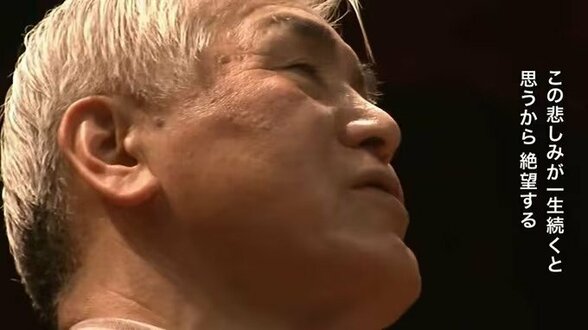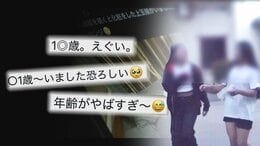実質賃金は14か月連続のマイナス
その一方で、物価が上昇しても、賃金が同じように上がらなければ、生活は苦しくなります。7日に発表された毎月勤労統計によれば、従業員5人以上の事業所の1人あたりの現金給与総額、つまり名目賃金は28万3868円と前年同月比2.5%の増加でした。しかし、実質賃金の算出に用いる物価(持ち家の家賃換算分を除いたもの)が3.8%もの上昇となったことから、実質賃金は前年同月比で1.2%の減少となりました。
実質賃金は、昨年4月以来14か月連続でマイナスです。とりわけショックなのは、今年の春闘で30年ぶりという高い賃上げ回答が相次いだにもかかわらず、新年度に入った4月も、5月も実質賃金がマイナスを続けていることです。要は、3%や4%の物価上昇は、高過ぎるのです。
賃金の上昇は、物価の上昇より遅れて実現するので、今年の後半には実質賃金がプラスに転じるという楽観的な見方もありますが、物価上昇が高止まりしていることから、先行きを不安視する声も少なくありません。
物価上昇で一番得をするのは政府
考えてみれば、名目物価が上がって一番得をするのは借金をしている経済主体です。日本最大の債務者は、赤字国債を出し続けている政府です。次に得をするのは、土地や株、モノを持つ経済主体でしょう。インフレで保有資産の価値も上がるからです。逆に、一番損をするのは、借金がなく、なおかつ資産を保有しない経済主体です。要は、普通の個人です。だからこそ、マクロ経済運営では「物価の安定」が何より重要なのです。
二度とデフレに戻りたくないので、しばらくは高めの物価上昇を容認したいという、政策当局の気持ちもわからなくはありませんが、そろそろ、「物価の安定」にしっかり目配せすべき時ではないでしょうか。それこそ、中央銀行に対する「信頼」に関わる問題です。