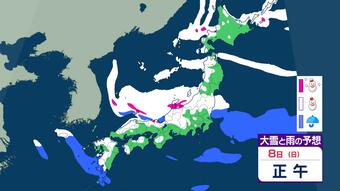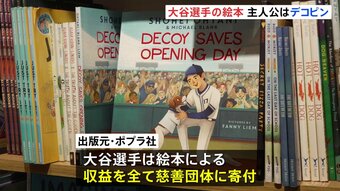(熊本学習支援センター仙波達哉センター長)
集団の中に自分がいる限界っていうのを感じているんだと思いますね。時代は変わっているのに、学校が変わらないというところに大きな問題があるのではないかと思います。家庭の居場所と学校の居場所以外に”第三の居場所”というのが必要な時代になってきているんです。
不登校の子どもが増える中、長年不登校対策を講じてきた文部科学省も方針を転換しています。「教育機会確保法(2016年成立)」によって「学校に戻ることが全てではない」としたのです。さまざまな学びの場を確保することを目標としています。
しかし、学校以外の場所を見つけるのは簡単ではないという指摘もあります。
(登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク中村みちよ共同代表)
親は学校以外に通える場所がないか探すもののなかなか辿りつかないという現状があります。民間のフリースクールや行政の支援施設もまだまだ数が足りません。気軽に学校以外の場所を選択できるような体制が整っていないのです。
■「いろいろな人の助けがあって学問の世界に戻れた」
ー今、不登校で悩んでいる子どもたちに伝えたいことはありますか
(磯田さん)
自分が不登校になった時はもう勉強の世界には戻れないと思っていましたが、そんなことはなくて。可能性がなくなったというふうに思って欲しくないです。僕にとっては人と違う経験をしたことで、自分のアイデンティティの形成に役立ったと今は思っています。実際、不登校だった間に初めて海外に行きました。不登校になったからこそ見えた世界があって全然マイナスにとらえる必要はないと思います。中学生の自分に伝えたいのですが、自分の興味と関心があれば勉強はどこでもできるのです。
磯田さんが通ったフリースクールでは、大学生のボランティアが中心となって個別に勉強を教えています。世代の近い大学生と話をする中で、共感してもらえたことも再び勉強に向き合うきっかけになったと言います。
ー将来的には何になりたいですか
(磯田さん)
不登校からまた学問の世界に戻って来られたのは、いろいろな人の助けがあってのことなので、不登校の子どものサポートをできることに関わりたいです。一番イメージしやすいのは学校の先生かなと思っています。学校でこういうところが嫌だったとか、もっとこうだったらいいのにとか、僕にしか見えないこともあると思うので、そういうところで役に立てたらと思います。
ーどういう支援が必要だと感じていますか
(磯田さん)
今は映像で配信したりという方法もありますし、そういったものを推進して学校という「場所」には合わなくても、学校という「機関」で勉強できるという支援があると、勉強で悩む子は減るのかなとは思います。